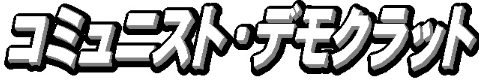福島県で進められている復興政策「イノベーション・コースト構想」が、「創造的復興」の名のもとに「経済安保」=対中軍事戦略強化のための、軍民デュアルユースを狙ったベンチャー企業群の「スタートアップ」、あらたな軍需産業育成を狙ったものであること、その司令塔が特殊法人エフレイであることをこれまで明らかにしてきた(本紙108号、114号 日米軍事同盟の基軸に据えられたエフレイ福島イノベ構想の狙いとその司令塔 | コミュニスト・デモクラット)
構想スタートから7年、その進展は凄まじい。フクイチを取り囲む大熊、双葉両町を中心に、浜通りでは山を切り崩しメガソーラーや工業団地が開発され、工場や研究所の建設が進んでいる。隈研吾設計の浪江町グランドデザインに代表される未来都市のような街づくりが進む。いずれは帰還したいと考える住民にとって「これは私が帰るような場所ではない」と言わせる変貌が進む。
日常的な監視活動や、案内ツアーで見えてきたものがある。それは参入している様々なスタートアップ企業の質と狙いだ。大別すれば以下の様になる。①当初から成功させる意図、意思もなく、復興関連補助金の食い逃げを狙う「補助金詐欺」的なもの、②当たれば大きな利益を得られるが失敗リスクが大きくテストプラント的な形で参入、③防衛省や経産省等と深く繋がり本格的軍事開発、新興軍需産業創出を狙う企業群、④街の「賑わいづくり」を狙う明らかに供給過剰の道の駅や飲食店街等に大別できる。いずれもが明確に区分けできるわけではなく境界は曖昧だが、共通するのは莫大な補助金や優遇措置に雑多な資本が群がる姿だ。
どれも問題にしなければならないが、特に危険性が大きく注視しなければならないのは、③に分類されるものだ。その典型的な例が曾澤高圧コンクリート㈱(以下、曾澤)である。
排他的経済水域に16万機の大ドローン防衛部隊を計画


曾澤の代表取締役社長曾澤祥弘は23年4月、ドローンと浮体式洋上風力発電をセットにした防災モデルをエフレイの講演会で発表した。洋上風力発電浮体の構造部にアンモニア自動供給システムを組み込み、排他的経済水域(EEZ)に4000艦配置し、ドローンの発着基地とすることで、16万機のドローン防衛部隊を作るという計画だ。
浮体部分で空気と水から電解水素を生成、アンモニアを合成、「CO2を出さない石油の代替燃料」で「21世紀の洋上グリーン油田」の実現を謳う。さらに、浮体の下部には藻場と漁場を形成し食料安保にも寄与できるとする。浮体式洋上風力を核に、エネルギー、食料、防衛の三兎を追う巨大構想だ。
曾澤はこの浮体艦を〝MIKASA〟と命名―日露戦争で勝利を上げた連合艦隊の旗艦「三笠」と重なる―、28年末の進水を目指す。本プロジェクトは大学・研究機関や企業40社が結集、指揮を執る北海道大学公共政策大学院客員教授の石井吉春氏は、このモデルを政府がインフラとして整備すべきと提唱する。
EEZは領海の外側から200海里(約370㎞)までの海域で、沿岸国は資源開発や海洋環境の保護など、特定の権利を行使できるが、領海とは異なり主権は及ばない。各国の航行の自由が保障される公海である。主権が及ぶ領海は沿岸から12海里(約22.2㎞)である。いくら「防災」「防衛」と主張しても、ドローンは容易に自爆型攻撃機にも変えることができ、武器システムとして使えることは、既にウクライナ戦争で実証済みだ。
日本のEEZはその西側が米国の防衛線と重なっている。アチソンライン(不後退防衛線)と言い、ディーン・アチソン元米国務長官が冷戦期の1950年に共産主義勢力を排除するための防衛ラインとして示した概念だ。2010年以降、中国を念頭に置いた新戦略として、台湾と韓国を含む形の新アチソンラインが西側論者の間で主張されている。EEZに浮体式洋上風力発電を配備することは当然中国の主権と対立する。対中戦争の口実を自ら作り出す好戦的で挑発的な計画だ。
今国会でMIKASAを後押しする法改正が成立
2025年6月、国会においてMIKASAの実現を保証するような法改正がなされた。「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」だ。そのポイントは以下の2点。①現在の「再エネ海域利用法」には、EEZについての定めはないため、EEZにおける海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る制度を創設する。②海洋環境等の保全の観点から適切な配慮を行うため、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の際に、国が必要な調査を行う仕組みを創設する。
中国でも米空母・原子力潜水艦の侵入を阻止する国防上の必要から、日本との間に第一、第二列島線という対米防衛ラインを引いている。公開されているこれらのラインと抵触するMIKASAは当然中国の反発を招き国際問題化するのは必然だ。それを承知でこのような法改正を行うのは戦争挑発そのものだ。②が示す海洋環境や地下資源の保全とは、同時に潜水艦戦を想定したデータの蓄積を目的としたものであるとの指摘もある。
コンクリート会社を軍需産業に変質させる実戦を視野に入れたインフラ整備
セメント業界は、製造工程で排出するCO2が多く、総排出量の数%を占める。このため各国で排出量削減が急務となっており、業界が生き残りをかけて新技術・新素材の開発にしのぎを削っている。曾澤は近年、コンクリート素材と先端テクノロジーを「掛け算」することで、脱炭素スマートマテリアル、防災支援インフラメンテ、スマート農業陸上養殖など6分野を掲げ急速に進出を図っている。21年8月、浪江町と立地協定を締結し、補助金20億円を得て、研究開発施設と工場が一体となったRDM(研究・開発・生産)センターを建設した。
コンクリートメーカー55社を集め、防衛施設市場への展開を図る政策集団を組織した。防衛施設では、老朽化が進んでおり、耐久性向上とメンテナンスコストの削減が急務となっている。曾澤が独自に開発したバクテリアによる自動修復機能を持たせた「自己治癒コンクリート」を、55社とライセンス契約し普及拡大を図る。これと併せてマサチューセッツ工科大学が基本技術を行ってきた、蓄電池の代替となる「蓄電コンクリート」を開発し、2万米ドルで50社とのライセンス契約を公募している。各メーカーは、これらの製品を使うことで「NET ZERO2045」(2045年の脱炭素実現)を自社ブランドに明示することができる。これらの企業との工業会形成により大手メーカーとの競合性を高め、滑走路、弾薬庫、地下シェルターなどへの展開を目指している。鉄からコンクリートへの代替も進めており、トランプ関税による鉄鋼石の価格高騰も、この狙いに拍車を掛けている。
戦前の軍国主義思想を体現する曾澤
23年7月、曾澤社長は岸田首相のサウジアラビア訪問に日本の財界40名余りとともに同行した。サウジは16年に脱石油戦略を打ち出し、ムハンマド皇太子を司令塔に建設産業の育成、経済のデジタル化などを進めており、すでに同国の企業と合弁事業を開始している曾澤が日本政府から同国訪問への同行を要請されたという。無名の一企業が、目を見張るほどの快進撃を続けるには別の要素がある。過去の中国侵略を反省せず、歴史歪曲、中国蔑視と反共を旗印とする極右政党化した自民党との親和性である。
25年6月、曾澤は札幌の劇場でドキュメンタリー映画『大和の赤子』上映会を主催し、曾澤社長が舞台挨拶で映画についての想いを観客と共有した。本作品(予告編)では、戦後米国が日本をアメリカ風に作り直そうとした変革の結果、若者がアイデンティティを喪失しているとして、「80年越しに過去の過ちを正す」、「失われた日本の起源を掘り起こし、国の心を取り戻す」としている。
日中友好・平和運動と福島イノベとの闘いの結合で対中戦争準備にストップを
一方で、MIKASAのEEZ配備は簡単には進まないだろう。中国の主権をあからさまに侵す計画は、中日間の政治外交問題に発展することは必至だ。技術的にも移動が困難な浮体式洋上風力発電は「敵」の反撃で容易に無力化される。自爆型ドローンの場合、その補給に本土からの海上補給に時間がかかる。4000基16万機の洋上のプラントおよび機器のメンテナンスをどうするのか等々。しかし油断は禁物だ。
全国の反基地運動は、南西諸島における長射程ミサイル配備、全国での弾薬庫拡大増強の動き等を通じて、日米支配層の対中戦争計画との闘いが重要であることの認識は広まっている。
一方で、福島原発事故の後始末、「復興」計画=福島イノベーション・コースト構想が、こうした支配層の対中戦争準備と密接にかかわっていることの認識は極めて不十分である。反戦反基地平和運動と福島イノベに反対する運動との結合は急務である。両者の結合した闘いで対中戦争準備にストップを掛けよう。
(WD/KA)