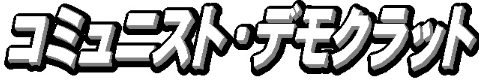政府は、東日本大震災・原発事故で壊滅的被害を受けた福島県浜通りの産業復興政策として、「イノベーション・コースト構想」(以下「福島イノベ」)を打ち出した。福島イノベは廃炉、ロボット、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療、航空宇宙など6つの重点分野に特化したハイテク産業誘致を進める政策である。
この司令塔として、特殊法人「福島国際研究教育機構」(F-REI、以下「エフレイ」)を浪江町に設置した。エフレイは、上記ハイテクの中で特に国家戦略上重要な分野に予算を付けて研究開発を促すための研究機関である。施設は未完成だが、先行して外部への委託研究を行っている。ハイテク(先進/先端/新興技術)とは、米国では軍事として扱われる分野である。
日米首脳会談によりエフレイが核を含む軍事同盟強化の中枢組織の一つに
2024年4月、日米首脳共同声明「未来のためのグローバル・パートナー」で「前例のない高み」の「防衛・安全保障協力の強化」が謳われた。付属「ファクトシート」には、エネルギー、ロボット、放射線科学、原子力災害に関する取組及び農業等におけるPNNL(パシフィック・ノースウエスト国立研究所)とエフレイの協力覚書が明示された。エフレイが日米首脳会談で声明として出されるレベルにまで引き上げられたのだ。PNNLは原爆開発のハンフォードに立地する核と軍事、ハイテクの研究所で、エフレイはこれをモデルとしている。
本年2月7日、両国首脳による共同声明「米国による核を含むあらゆる能力を用いた、日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメント」が発表された。二つの共同声明からは、エフレイが米の指揮のもと核開発と使用までを視野に入れた日米軍事同盟の新たな中枢組織の一つとして正式に位置付けられたことを意味する。
エフレイは「福島復興再生特措法」の下で「新産業創出」の司令塔として2022年に発足した。「福島復興」の名目で防衛省とは別建てで核開発・核戦争をも視野に入れた組織が惨事便乗で進められている。
経済安全保障「特定重要物資」の研究開発・生産拠点としての福島イノベ
政府は、中国を仮想敵とする米国の安全保障政策と連動し2027年度までの5年間で防衛費43兆円を予算化した。軍民両用の科学技術開発・イノベーションが激化する一方で戦時を想定した国民生活や経済活動にとって特に重要な物資・技術分野を強靭化するため、2022年に経済安全保障法を成立させた。特に重要な物資・技術を次のとおり指定した。
①特定重要物資(ロボット、航空機部品、半導体、肥料、蓄電池、重要鉱物等12項目)
②特定重要技術(宇宙・海洋・量子・AI・サイバー等50項目)
①は、中国に多くを依存しているが、中国を排除し、同盟国・同志国内での供給を目指すとしている。福島イノベは経済安保の研究開発と生産拠点づくりの場となっている。
核戦争下でのキーデバイス – ダイヤモンド半導体
エフレイの研究で期待されているものの一つに、ダイヤモンド半導体がある。人工ダイヤモンドを使った半導体は、高温や低温、放射線などの極限環境に強いことから、放射線が飛び交う過酷な環境である原子力発電所や宇宙環境において、優れた性能と省電力性が両立できるとされ、電気自動車、次世代通信基地局(6G)、軍事などへの応用が期待されている。2022年、北海道大学と国立研究開発法人産業技術総合研究所によるスタートアップ企業「大熊ダイヤモンドデバイス株式会社」が大熊町に進出。同社は、投資家から資金を集め、創業わずか2年半で約67億円を調達、同時に、経済産業省の「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」も獲得した。本補助金は、福島県の避難指示解除区域等で工場等の新増設を行う企業に対して最大50億円を支援するものだ。
エフレイから同社に委託された研究は、「廃炉向け耐放射線性に優れたダイヤモンド半導体の要素技術開発」という事業名で2024年から7年間、最大で49億円の研究費が付与される。実施体制は、大学、研究機関、同社、高専からなるコンソーシアム(共同事業体)だ。
経済安保「特定重要物資」の安定供給を行う事業者は、金融支援や官民連携の伴走支援が受けられる。支援策のベンチャー企業版「J-STARTUP」制度に、大熊ダイヤモンドデバイスが選定された。
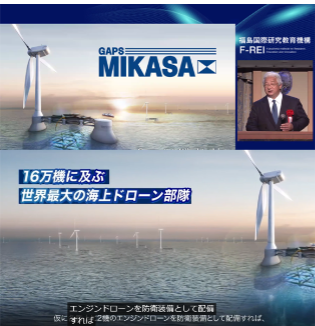
軍民両用のロボット開発の推進
エフレイ委託研究「フィールドロボット等の市場化・産業化に向けた性能評価手法の標準化事業」も重要な意味を持つ。委託先は日刊工業新聞社、研究費は3年間最大4.8億円だ。目的は2つ。まず災害対応・インフラ点検ロボットに関して、市場化・産業化、法整備に向けた性能評価手法の標準化を行うこと。次に2025年度ワールドロボットサミットに向けた競技内容の設計、採点基準等の検討を行うというものだ。日刊工業新聞社は、この2つと同時にワールドロボットサミットのスポンサーとなって利益の最大化を図っている。
実はこれには伏線がある。2014年、当時の赤羽経産副大臣が米国国際標準技術研究所(NIST)を視察し、アドバイスを受けているのだ。以下、赤羽報告より引用。
①NISTの付属施設ロボットテストファシリティ
・本施設は、都市における人命救助、爆弾処理、軍事作戦等への活用を想定したロボットについての試験施設であり、様々な現場を模擬したセットが設置されている。
・NIST は標準化機関として、ロボットの試験方法についての標準化を行うことで、開発者とユーザーをつなぐ役割を果たしている。最近では、ワシントンDCの爆弾処理ロボットや国防総省の軍事用ロボットの調達に関して、ロボットの性能評価を行う技術支援を行った。
②略
③DARPA ロボティクスチャレンジについて
・米国防総省下の国防高等研究計画局(DARPA)の主催する災害対応ロボットのイベント形式での研究支援プログラム。達成すべき課題を設定し、優勝した者に賞金200万ドルを与える。米国外からのエントリーも可能で、選抜されたチームは期間中DARPAから助成を受けられる。
・現在開催中のチャレンジ(2012年~2014年)は、震災直後の福島第一原発のように、人が作業できない過酷環境を想定した課題設定がされており、日本からも1チームが出場し、現在暫定1位。 (注:当時)。
・昨年7月、経済産業省と米国防総省は人道支援・災害対応ロボットの共同研究の実施に合意。平成26年度より共同研究を開始する予定。今後、日本でのチャレンジ開催についても期待が表明された。(引用ここまで)
赤羽氏の帰国後、南相馬市に「ロボットテストフィールド」が創設された。

ロボットテストフィールドをエフレイに統合
ロボット競技会は上記DARPAから引き継ぐ形で、福島原発事故の後始末対策として「廃炉創造ロボコン」が2016年より毎年開催されている。全国の高等専門学校に廃炉ロボット技術を競わせるものだ。(主催は文部科学省と廃止措置人材育成高専等連携協議会)DARPAとは、軍用技術の開発および研究を行うアメリカ国防総省の特別の機関であり、インターネットやGPSを開発したことで知られる。2024年10月、防衛省は防衛装備品の開発強化のため、日本版DARPAを標榜する「防衛イノベーション科学技術研究所」を都内恵比寿ガーデンプレイスに創設した。
2025年よりロボットテストフィールドはエフレイに統合された。ここで「廃炉創造ロボコン」とは別に新たにワールドロボットサミットが開催される予定だ。テーマは「過酷環境F-REIチャレンジ」(賞金5千万円)。スポンサー企業のほかに、協力団体として日本ロボット学会、人工知能学会、日本機械学会なども関与する産官学一体型である。エフレイ下で「廃炉」から「過酷環境」へ、新たな軍民両用開発のロボコンが始まる。
・・・・
福島イノベ、そこには大きく3つの意図がある。まず原発事故からの復興を内外に強力にPRし原発事故の矮小化を図る。第二にハイテクに特化した分野を推進することで、産業化と軍事転用の二兎を追うものだ。第三に、未だに放射能汚染度が高く若い世代が帰還しないことを逆手にとり広大な敷地を確保、対中戦争下を想定した特定重要物資の生産拠点づくりだ。原発事故加害企業や国は責任を免れ、惨事に便乗したビジネスで荒稼ぎする。米国に追随する産官学一体の利益共同体による、危うい未来への誘導を阻止しよう。
(WD)