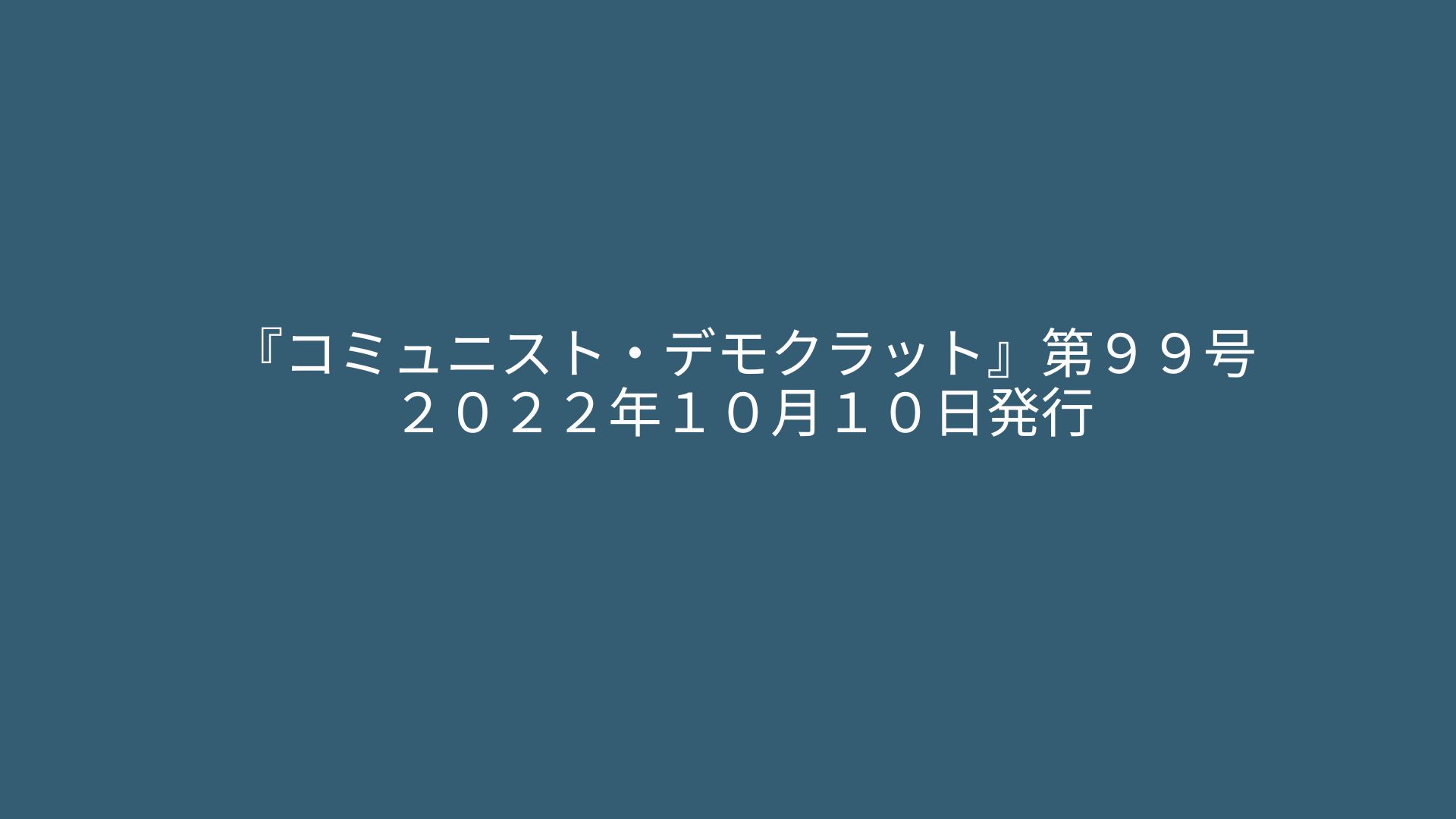エリザベス2世が9月8日、死去した。以来、日本のニュースやワイドショーは、連日、女王を礼賛、「功績」を称える異様な報道に終始した。国葬当日、日本のテレビは特番を組んだ。翌日の新聞朝刊は「英女王 世界が別れ」「英女王国葬 世界が追悼」「英国の母 最後の別れ」「荘厳な葬列」等々で埋め尽くされた。リベラルの一部にも、「民主的で開かれた王室」「明るい王室」に親近感を持つ人もいる。
しかし、それは西側政府・メディアが作り上げた偶像、虚像だ。国葬は、イギリス君主制とイギリス帝国主義を称えるセレモニーであった。21世紀の今日にも残る、日本の天皇・皇后を含む前近代的・半封建的な時代の残滓のような君主が世界中から集まった。バイデン米大統領や英連邦と関わりのある西側帝国主義の代表が参列した。
女王の国葬は、イギリスの金融独占ブルジョアジーによる階級支配の道具であることを明らかにした。国葬の一時期、右も左もなくなった。議会は全て王党派となった。議会は10日間停止し、保守党員だけではなく、労働党員も女王への賛辞を捧げた。インフレ・物価高、格差・貧困の是正の議会論戦は棚上げとなった。郵便・鉄道労働者は、賃金と労働条件をめぐって計画していたストライキを取りやめた。労働組合のナショナルセンターである労働組合会議(TUC)は大会を延期した。立憲君主制の階級協調主義機能は遺憾なく発揮された。
われわれは、今回の女王の死去と国葬を、今日のイギリスを作り上げた大英帝国の植民地支配・人種差別・奴隷制度・虐殺と略奪の歴史的犯罪を断罪する機会としたい。女王は、植民地支配の残虐行為一切に対して謝罪も賠償もしていない。女王の死を機に大英帝国の旧植民地から怒りが噴出している。この怒りの声を拾い上げ、その犯罪性を訴えていきたい。イギリスが民主主義国でも何でもなく、国王を頭に頂く、白人至上主義的・人種主義的、非民主主義的な君主制の国であることを暴露する。今日のイギリス帝国主義が、英連邦を形成するその膨大な旧植民地の民族独立・民族解放の歴史とともに没落していることを明らかにしたい。
これらのこと一切は、象徴天皇制日本帝国主義の中で生きて活動するわれわれにも無縁ではない。現在の天皇は、明治天皇から昭和天皇へと続く、天皇制軍国主義による侵略戦争と植民地支配の全ての責任を引き継ぐ。女王の死に際して、これをわれわれ自身の問題として受け止め、日本の戦争責任の追及に取り組み、象徴天皇制の廃止を訴えていきたい。
イギリスは立憲君主制国家ー民主主義国家ではない
イギリスには国王主権が色濃く残り、国民主権が徹底されていない。君主の存在そのものが民主主義と相容れない。それは、差別と特権、人種差別、階級を前提とする階級社会、差別社会の集中的表現である。しかも、それが一定の政治的権能を持てばなおさらだ。
今日でも、イギリスの国王大権は重要な分野に及んでいる。「国王」または「女王」は、軍隊の最高司令官である。今回の国葬でも棺を囲む王族は男性も女性も軍服に身を包んだ。議会の解散や停会、首相・大臣・軍人・裁判官などの任免権を有し、英国国教会の首長だ。日本では戦後憲法で廃止された貴族院がイギリスでは今も続く。貴族制度があり、世襲貴族が800家以上ある。いったい、これのどこが民主主義国なのであろうか。国王の大英帝国は姿形を変えて今も続く。英連邦王国(Commonwealth realm)は15ヶ国ある。カナダやオーストラリアやニュージーランドなどだ。中国やロシアに対して「権威主義」「独裁」と悪罵を放つが、これらの国々の元首は自国の首相ではなく、英国王だ。これとは別に、旧英国植民地を中心とした56ヶ国英連邦(Commonwealth of Nations)があるが、この連邦の長も英国王である。
国家元首である英国王ー70年の治世全てに責任を負う
英国の国王は国家元首である。すなわちエリザベス2世は、1952年の戴冠以来、70年間に及ぶ在任中、英国政府のあらゆる政策に責任を負っていた。
英国王の政治的権能は限定され、基本的には政治に直接関与しない象徴的な存在と言われる。だが、エリザベスが女王に就任した時代、1950年代から60年代は、第二次世界大戦後の民族独立と社会主義世界体制確立の時代であった。それまでフランスと並び世界中に植民地を保有したイギリス帝国主義が植民地独立で危機に陥った時代であった。この危機感を彼女も共有し、元首として、英植民地からの独立闘争への軍事介入、弾圧に直接間接に関与した。それまでの英国王と同様、エリザベス2世の治世も血にまみれたものであった。西側政府・メディアの女王への礼賛に、英連邦の左翼・共産主義者・民主主義者から一斉に女王治世の暴虐に抗議の声を挙げている。以下は、その一部だ。
マラヤ危機(1948~60年)。在任前から在任後の12年にわたるマラヤ共産党の植民地独立闘争に対する虐殺と弾圧だ。英植民地政府は非常事態宣言を出し、40万人~100万人を強制収容所に収容し、農民を虐殺し餓死させた。
マウマウ独立蜂起への弾圧(1952~60年)。イギリスの白人入植者がケニア住民から土地を奪い、入植地に変え、強奪した農地で現地住民を農業労働者として酷使したことにケニアの住民は反乱を起こした。イギリス軍は9万人を虐殺し、拷問し、16万人を強制収容所に閉じ込めた。現在、ケニアの被害を受けた部族は、土地の窃盗と植民地犯罪の賠償として、イギリス政府に2千億ドルの賠償金を求めている。
モサデク政権転覆クーデターと王政復権(1953年)。民主選挙で選ばれたモサデク政権が、イランの石油はイラン人民のものだと主張し、イギリス資本のアングロ・イラニアン石油会社を国有化しようとした。これに激怒した米英が結託して軍事クーデターを起こした。英米の陰謀によってシャー・パフラヴィ国王が復権した。エリザベス2世は1959年にシャーを国賓として招き、61年にイランに国賓訪問し、王族同士の結束を強め、シャーの軍と秘密警察による残忍な独裁体制を公然と支持した。
イエメンでの秘密戦争(1962~69年)。1962年、イエメン国王の死後、アラブ民族主義者が政権を掌握し、共和制を宣言した。これに王族が中東の王政とイギリス軍の支援を受け反撃した。1969年時点で20万人の犠牲者を生み出した。
血の日曜日(1972年)。北アイルランドでイギリスからの分離とアイルランドへの統合を求めていたカトリック系住民のデモにイギリス軍が発砲し、13人を虐殺した。
米英のディエゴガルシア島密約(1971年)。インド洋南西部のディエゴガルシア島に米軍の空軍基地を建設する米英の密約により、イギリス軍の脅しと暴力で住民が追放された。女王の枢密院議員(顧問)の決定を経て、女王によって直接承認が下された。イギリスはこの見返りに、米海軍のSLBMポラリスを格安で供給してもらった。同基地は1991年の湾岸戦争、2001年のアフガニスタン戦争、2003年のイラク戦争で出撃拠点となった。
エリザベス2世が南アのアパルトヘイト体制に反対したという言説はウソだ。南アを植民地化したのも、人種隔離体制を制度化したのも国王の政府、女王の政府であり、彼女は在任中一度も南アとその人民に謝罪しなかった。南アのアパルトヘイト体制を女王の政府の弾圧や妨害に抗して打倒したのは、膨大な犠牲者を出して闘った南ア人民の功績である。
これらのおぞましい植民地主義的犯罪はごく一部に過ぎない。英国政府は、1950年代から70年代にかけて、「レガシー作戦」を展開した。独立前の植民地行政の記録を全て焼却・廃棄する証拠隠滅工作だ。「女王陛下の政府に恥をかかせる」というのが理由だという。
残忍かつ血なまぐさい侵略、虐殺、略奪で繁栄した大英帝国
エリザベス2世は、1921年に地球の全領土の4分の1を支配した大英帝国の最盛期の支配権と栄華をどう防衛するかに腐心した。その起原はエリザベス1世の時代(1558年~1603年)に遡る。それ以前、イングランドの威光が及ぶのは隣国アイルランドだけだった。彼女は貴族や海賊を使って太平洋でポルトガルやスペインの商戦を襲撃し、金銀財宝やアフリカ人奴隷を強奪しまくった。すでに広大な植民地を領有し、奴隷を強制労働させた略奪者ポルトガル、スペインから、さらに略奪した。泥棒の盗品を横取りしたのだ。泥棒の中の泥棒と言ってよい。王室の財政とイギリスの富の源泉は、海賊に盗ませた略奪品の転売であり、海賊と結託した黒人奴隷の略奪・密輸であった。東インド会社を設立したのも、その出資金を出したのも海賊だった。貿易商人と海賊は一体のものだった。いわば、大英帝国は泥棒国家である。ノブレス・オブリージュ(高貴さは社会的義務を負う)とは、このような残酷な略奪を覆い隠す隠語なのだ。
英女王がカリブ海の小さな国バルバドスでのサトウキビ大規模植民地経営から収奪した富は大英帝国誕生の第一歩となった。ここで酷使した奴隷の数は、累積で言えば北米大陸の奴隷総数に匹敵するほどだった。大英帝国の基礎はインドではなくカリブ海諸国であった。近代ヨーロッパが経済的・軍事的に突出した発展を遂げたのは、カリブ海や南北アメリカ大陸におけるヨーロッパ列強の奴隷制度であった。イギリスに資本主義を確立した産業革命は三大発明が生み出したと言われるが、それは違う。実際にはマルクスが『資本論』第一部第24章「いわゆる本源的蓄積」で解明したように、一方での大量の資本の蓄積と、他方での「自由な」労働者の創出だ。そしてその大量の資本の蓄積の最大の源泉こそが、資本主義制度の「台座」としてのカリブ海の奴隷制度と結びついた略奪的な「植民地制度」なのである。
「ヨーロッパでの賃金労働者の隠蔽された奴隷制は、その台座として、新世界での 〝露骨な〟奴隷制を必要とした。・・・資本は、頭から爪先まで、あらゆる毛穴から血と汚物とをしたたらせながらこの世に生まれてくる」(『資本論』24章「いわゆる本源的蓄積」)
奴隷制度の上に打ち立てられた大英帝国は、民主主義や人権とは無縁な存在である。インド総督を歴任した英貴族は富を本国に吸い上げ、世界中で戦争をする戦費を賄うため、インド農民に悲惨な飢饉の中で重税を課し、多くの犠牲者を出した。
イギリスは、インドで製造したアヘンを清に輸出して莫大な利益を得ていた。アヘン販売を禁止した清は、全面禁輸を断行し、イギリス商人のアヘンを没収・処分したことから戦争が勃発する。アヘン戦争だ。英軍に敗北した中国は香港の割譲を余儀なくされる。中国の屈辱の始まりである。
英国王の金銀財宝も植民地からの略奪が多い。新国王チャールズ3世が相続した土地は66億エーカー、少なくとも約280億ドル。モロッコ国王やローマカトリック教会が所有する土地の約40倍、サウジ国王の12倍以上に及ぶ。王室の総資産は880億ドルという。1970年代、贅沢な暮らしをしていた女王は姑息にも莫大なこの私財をイギリス国民から隠すために政府に法改定を働きかけたという。
イギリスの植民地支配を雄弁に物語る物がある。戴冠式で使われる王冠と王笏に埋め込まれた巨大なダイヤモンドは、1905年に南アフリカで発掘された世界最大の原石からカットされた。これらには「英国が盗んだのだから返還すべき」と南アから要求が出されている。また世界最古と言われるダイヤ「コイヌール」も王冠を装飾するが、これもまた原産地インドからは「盗まれた」として独立以降、返還を求められているが、イギリスは一貫して拒否したままだ。それだけではない。大英博物館の展示品の多くは、エジプト、インド、南アなどから、政府の職員が英軍艦を使って盗み出した盗品だ。盗品を返却すれば、大英博物館から展示品がなくなると言われている。
イギリス帝国主義の没落と噴出する英君主制批判、共和制への動き
エリザベス女王2世の死とリチャード3世の就任は、英国内外で君主制に対する批判を再燃させている。英議会議事堂の前では「あなたは私の王ではない」「君主制廃止」とのプラカードを掲げた人たちが抗議行動を行った。スコットランドやオックスフォードでも抗議行動があり、警察の弾圧に批判が起こった。今年5月の世論調査では、英国王制を支持する層の比率は70%から60%に減少、とくに若手層では30%に過ぎない。
共産主義者は公然と君主制廃止を掲げ、「民主主義革命を完遂する時が来た」と声明を出した。「1688年の反革命によって逆転された民主主義革命を完了する時期はとうに過ぎている」と。イギリス共産党は、綱領で、「人民主権とは、人民が選挙で選んだ議会、政府の代表、大衆運動における人民の主権を意味する」と述べ、「国家元首や軍最高司令官などのポストを含む君主制に関連するすべての権限と制度を、王室の特権、貴族院、そして同様に責任を負わない国家機関とともに廃止することが必要である」と主張している。イギリス青年共産主義者同盟も同じく「君主制の即時廃止と、民主的に選出された国家元首への置き換えを要求する」との声明を出した。
女王の死を利用した服喪の強要はわずか10日間しか効力がなかった。10月に入り、労働運動とストライキ闘争はかつてない高揚を見せている。人民を服従させる立憲君主制の政治的機能は明らかに減退している。
もはや君主制の力を借りても、イギリス帝国主義の没落は避けられない。金融帝国イギリスは通貨・金融危機の爆発に直面している。サッチャーを信奉し、新自由主義政策を強行した新首相リズ・トラスは、早々と富裕者減税を撤回せざるを得なくなり、就任早々政治的危機に陥っている。前首相ジョンソンから引き継いだ大英帝国の復活(グローバル・ブリテン)戦略は夢想でしかない。
とりわけ旧植民地から君主制批判が吹き出している。カリブのアンティグア・バーブーダの首相は、3年以内に立憲君主制の廃止と共和制に関する国民投票を実施すると表明した。ジャマイカやベリーズでは、過去の植民地支配に対して謝罪や賠償を求める活動が活発化している。バルバドスが昨年共和制に移行している。
今日の世界史の発展段階は、1950年代から60年代の旧植民地全体を捉えた民族独立の時代、1970年代のアフリカ革命、中米革命の時代に次ぐ、旧植民地諸国の経済的自立の時代にある。牽引しているのは、かつてイギリスがアヘン戦争で植民地にした中国である。社会主義中国が一帯一路政策を通じて、G7に代表される3大帝国主義による収奪と制裁にさらされる途上諸国のインフラ基盤を援助し、自立を促しているのだ。英連邦の途上諸国全体が含まれる。エリザベス1世時代の17世紀の境目以降に構築された大英植民地帝国は、四百数十年を経て没落し、根底から揺らいでいる。最近のイギリス政府の対中「新冷戦」、対ロシア戦争のエスカレーションは、この歴史的没落に対する絶望的な反動的巻き返しである。
(KM)