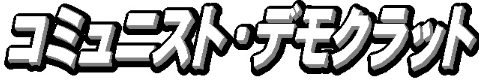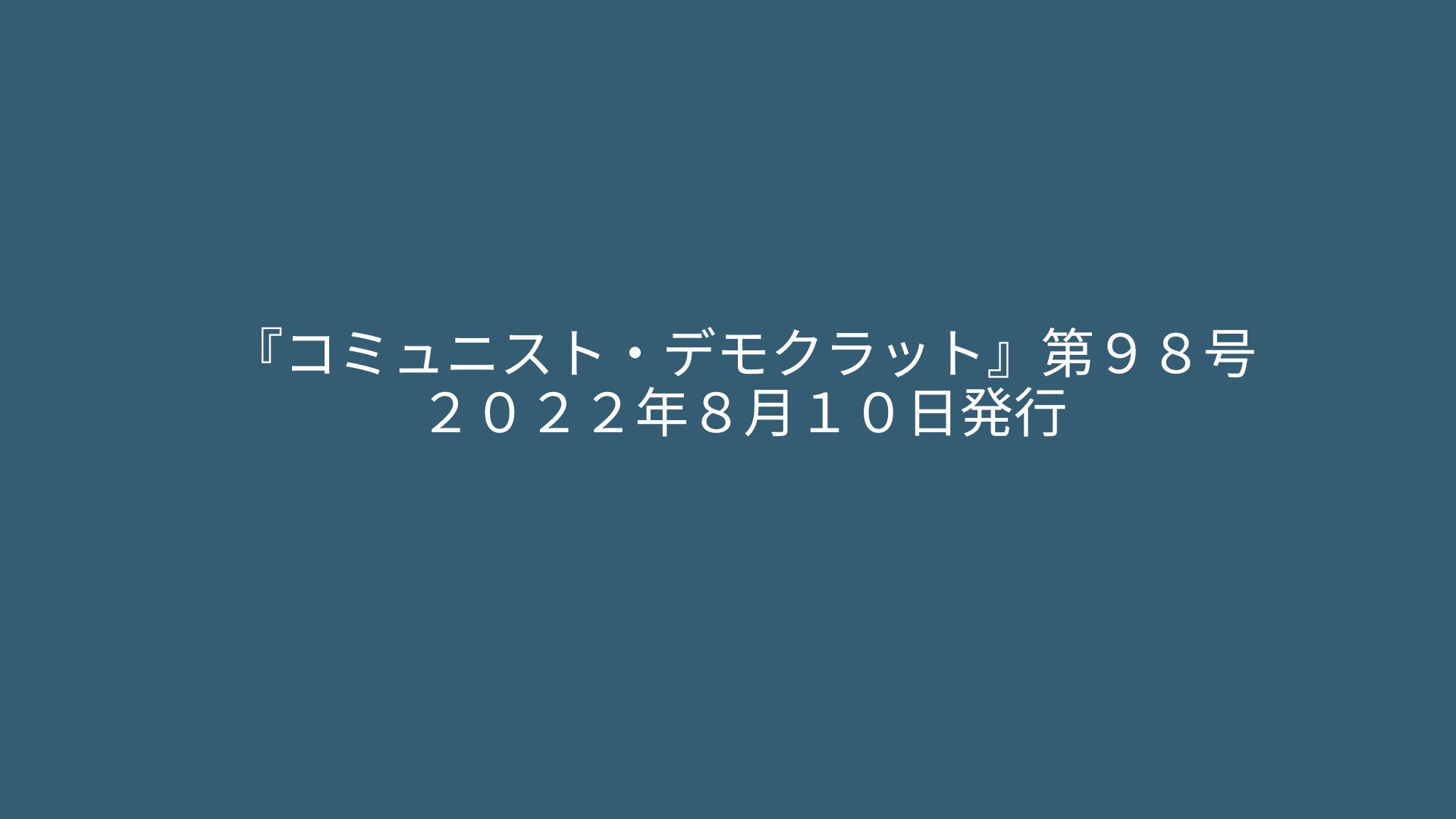8月7日、ペトロ大統領・マルケス副大統領の就任式が行われ、コロンビア初の左翼政権が誕生した。さまざまな妨害や暗殺の危険を乗り越えての快挙である。その基本性格は、反米反帝・反ネオリベ・民族解放の統一戦線政権である。それは、コロンビアにとってだけでなくラ米カリブ全体にとっても画期的な意義をもつ。第一に、ラ米カリブにおける米帝国主義の政治的軍事的橋頭堡で、ラ米で唯一のNATOグローバル・パートナーシップ国であるコロンビアで、左翼勢力が政権を獲得したということ。第二に、ラ米カリブの歴史的なラティフンディウム(大土地所有制)の典型的な国コロンビアで、オリガーキーと米帝による支配に風穴を開けたということ。第三に、長期にわたる多大な犠牲を払った闘争の成果であり、ラ米カリブ全体で生じている人民闘争の新たな一大高揚と前進の重要な一翼として、それをいっそう推し進めるものであるということ。
だが、国の政治・軍事と経済は未だ完全に米帝=オリガーキー反動勢力が掌握している。それと闘いながら前進していかなければならない。まずは閣僚選定と議会対策から前進の基盤を構築しようとしている。新たな闘いが開始されている。
(小津)
予想をくつがえしての決選投票での逆転勝利
5月29日の大統領選ではグスタボ・ペトロが得票率40%強で第1位であったが、6月19日の決選投票へ向けて2~4位の候補者が反ペトロで手を結び、反動勢力は総結集して政権を維持しようとした。この時点で得票率は40%対55%以上の差となり、数字上は反ペトロ連合が圧倒的優位の状況となった。しかし、わずか3週間の選挙期間でペトロとマルケスは大きく得票を伸ばし、決選投票では50・4%を獲得する逆転勝利を勝ち取った。それも選挙期間中に何度も命を狙われ、その支持者の活動家が多く検挙・拘束され、また準軍組織に殺害された中での勝利である。これは、アフロ・コロンビア人で女性人権活動家のマルケス副大統領への絶大な支持があったこと(後述するが「マルケス現象」とまで言われた)、そして昨年2ヵ月にわたって闘われた反増税・反IMFの大闘争の下地があったことによる。
全権力の一部掌握の下で予想される諸困難 閣僚選定で譲歩し新議会で多数派に
大統領選での勝利は画期的な意義をもつものではあるが、国家権力の一部、大統領という行政権力を掌握しただけであるので、立法権力(上下両院)、司法権力、軍・警察という暴力機構は、米帝と一体化したオリガーキーが握っている。経済は米系グローバル金融資本とオリガーキーが支配している。これらはすぐに手を付けるのが難しく、まずは議会での多数派形成と活動家殺害の暴力の追放を優先させようとしている。今後、強大な反動勢力と闘いながら、多くの困難を乗り越えていかなければならない。
議会については、3月に行われた議会選挙でペトロの与党「歴史的盟約」が最大の党派となったが、単独では過半数に遠く及ばない。反動勢力は大幅に後退したが未だかなりの勢力を保持している。7月20日に発足した新議会において、「歴史的盟約」は108議席の上院で20議席、188議席の下院で28議席の勢力である。
「歴史的盟約」は、コロンビア共産党、愛国同盟(元FARCが結成)、コロンビア労働党、先住民・社会代替運動、コロンビア・ウマナ(ペトロがつくった党)など、左翼のほぼ全域にわたる政党で形成されている。ペトロは、新政権の閣僚を決めていく過程で、「歴史的盟約」外からも進歩的民主的な人材を幅広く登用する形で複数の党の支持を取り付けた。その結果として、上院で108人中63人、下院で188人中114人の支持を確保した。
7つの米軍基地と50以上の「準基地」 コロンビア軍は米軍の指揮下に
25年前にコロンビアと米国との間で協定「プラン・コロンビア」が締結され、コロンビアは米国の軍事投資が第3番目に多い国になった(イスラエルとエジプトに次ぐ)。その上に、ウリベ政権下の2009年に新たな条約が締結され、7つの米軍基地が開設された。だが、政府とコロンビア革命軍(FARC)の和平交渉に出席した「歴史委員会」の一員であるコロンビア国立教育大学のレナン・ベガ教授によると、コロンビアには50ヵ所以上に米軍部隊が配置されており、それらは「準基地」と呼ばれている。さらに、CIAや「麻薬取り締まり局(DEA)」を筆頭に25の米秘密機関があって、日々自由に活動し、「経済、政治、社会、文化の面でこの国に介入している」という。その秘密性から、正確な把握は非常に困難であるが、コロンビア軍は米軍の指揮下にあるという。
コロンビアは軍事国家である。多くのコロンビアの軍人と警察官が米国で訓練を受け、「敵対者を拷問し、殺害し、行方不明にする」ことが教えられている。コロンビアでは、警察は国防省の指揮下にあり、事実上、軍の一部となっている。その上に、軍の統制下にある準軍組織(パラミリタリー:表向きは民間組織)がある。準軍組織は、正規軍に匹敵するほど多数で、大土地所有者の私兵であり、左翼・共産主義者、農民運動活動家を虐殺してきた。コロンビア革命軍(FARC)や民族解放軍(ELN)の武装闘争は、この準軍組織に対する自衛闘争であった。準軍組織は、また、米国マイアミのラ米右翼とも密接に結びつき、ラ米カリブ各地(特にベネズエラ)の極右とも結びついている。軍のまわりには、大手メディア、大学、病院、航空会社、輸送会社、銀行などが協力者として存在している。
コロンビア軍・警察-準軍組織-オリガーキー(大土地所有者、メディア、経済界)がコロンビアの支配階級であり、これらすべてに米政府・米軍と米系グローバル金融資本が食い込み、従属させている構図だ。
それだけではない。コロンビアは、チャベス政権時代からベネズエラのボリバル革命を叩き潰すための反革命介入基地であった。そして、米トランプ政権が2019年に画策したクーデターで担ぎ上げたグアイドが、米政府の指示でベネズエラの野党を指揮した拠点もコロンビアであった。米政府がコロンビアを自由自在に使えないことは、ラ米カリブの進歩的・革命的過程にとって大きな前進となる。
人口の10%が有効土地の86%を所有
ラティフンディウムとグローバル金融資本の経済支配
コロンビアの総人口は約5000万人で、アフリカ系の住民(アフロ・コロンビア人)は公式には450万人とされているが、アフリカ系コミュニティによる人口調査では全人口の4分の1、約1250万人である。政府統計では多くがメスティーソ(先住民と白人の混血)に分類されているという。アフロ・コロンビア人の多くはカンペシーノ(貧農)である。生活改善の要求を実現させようとして組織化すれば、テロリストとされ、弾圧され、殺害される。そして、治安部隊、準軍組織による殺害は責任追及されないのである。
アフロ・コロンビア人が多いチョコ州では、4人に3人がアフロ・コロンビア人である。ここは、かつてスペイン統治時代の「逃亡奴隷」が多く住み着いた所である。その多くが農業に不向きな土地のため仕方なく砂金採取を重要な収入源としてきた。だが、多国籍企業による鉱物採取が自然と人間を破壊し、住民を追い出してきた。その地域には、さまざまな鉱物資源、木材、石油などが豊富にある。居住地から追い出された人々は、多くが近辺の都市周辺で貧農として暮らすようになった。また、アフロ・コロンビア人の貧農の多くが1990年代に集団的土地所有の権利を勝ち取った。だが、その人々もグローバル資本の進出の中で多くが追い出された。そういう人々が先祖代々の土地を取り戻そうとする闘いが広範に行われるようになってきている。
アフロ・コロンビア人の長期の闘いと「マルケス現象」
大統領選での勝利に大きく貢献した副大統領フランシア・マルケスは、アフロ系女性の戦闘的な人権活動家・弁護士で、貧困の中で育ち、13歳のころから親たちの闘いに加わってきた。説得力のある語りで大衆を、特にアフロ系住民、女性、若者を引きつけた。マルケスは、暴力と組織的不平等のシステムの解体を「歴史的盟約」が提案していることを強調し、その最初のステップは国民参加型の政府計画であるとしている。その下で経済を改善していくこと、戦争予算を削減し、健康、教育、住宅、仕事の予算を増やすことを主張している。
マルケスは、スペイン統治時代の「逃亡奴隷」の末裔である。帝国と奴隷商人の支配と抑圧から脱却しようと逃亡した人々が、辺境の地でコミュニティを形成し、今日に至るまで抵抗と闘争を続けてきたが、マルケスは、その人々の価値観を今において代表している一人である。選挙のときに、アフロ系住民の多い都市では国家暴力による投票妨害が行われたが、その下で投票率は以前より大幅にアップした。それは「フランシア・マルケス現象」と呼ばれた。これまでは選挙を諦めていた多くの人々が投票に向かったのである。
内戦の完全終結と人民生活の改善 ベネズエラとの国交正常化
ペトロは、まず内戦に終止符を打つことを最優先課題としている。2016年のFARCとの和平協定後も、社会活動家約1000人、元FARC戦闘員約300人が殺害されている。内戦の完全終結は圧倒的な国民が支持している。まだ武装闘争を続けている組織もペトロの勝利と新政権を評価しており、和平の完全実現に期待が高まっている。
国内政策でのペトロの他の公約は、飢餓に対する緊急計画、ホームレスへの住宅供給、高齢者のための年金の確立、無料で質の高い公教育、農地改革と農村部の生産性向上、税制改革、エネルギー産業改革、それらを通じての経済回復、環境への配慮、芸術・文化の振興などである。そのほかに、汚職を抑制するための委員会の設立や、公的機関での女性の50%登用、さらに軍・警察・準軍組織による人民への暴力に対する不処罰の解消も主張している。
ペトロ政権は、現時点では社会主義指向ではないが平和と社会正義と民主主義の徹底を強く主張している。農村部の大土地所有と軍事的暴力的支配とは不可分に結びついている。それらを解体し解消していくためには、本格的な農地改革や準軍組織の解消を含む軍・警察の改革が必要であり、これまで以上の闘いが要求される。
対外政策はあまり多くは報じられていないが、社会主義指向ベネズエラとの国交を正常化し、国境での紛争をなくすことを優先的に行おうとしている。7月28日にアルバロ・レイバ次期外相がベネズエラを訪問し、新政権発足の8月7日から外交関係を回復させる取り組みが早々に開始された。
今回の勝利は、多大な犠牲を出したコロンビア人民の長い闘いの成果である。特に昨年4月末からの2ヵ月を越す全国ストなどの大闘争は、労働組合を中心としたそれまでの闘争をベースにしながらも、新しい世代の若者、女性、アフロ系住民・先住民などが多く参加し、一大飛躍を遂げた。それは、IMFが主導した右翼政権による大増税に反対したものであった。その持続といっそうの発展の中での今回の大統領選勝利である。今後、さまざまな困難を一歩一歩乗り越えながら、さらに前進していくに違いない。といっそうの発展の中での今回の大統領選勝利である。今後、さまざまな困難を一歩一歩乗り越えながら、さらに前進していくに違いない。