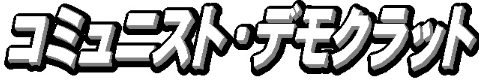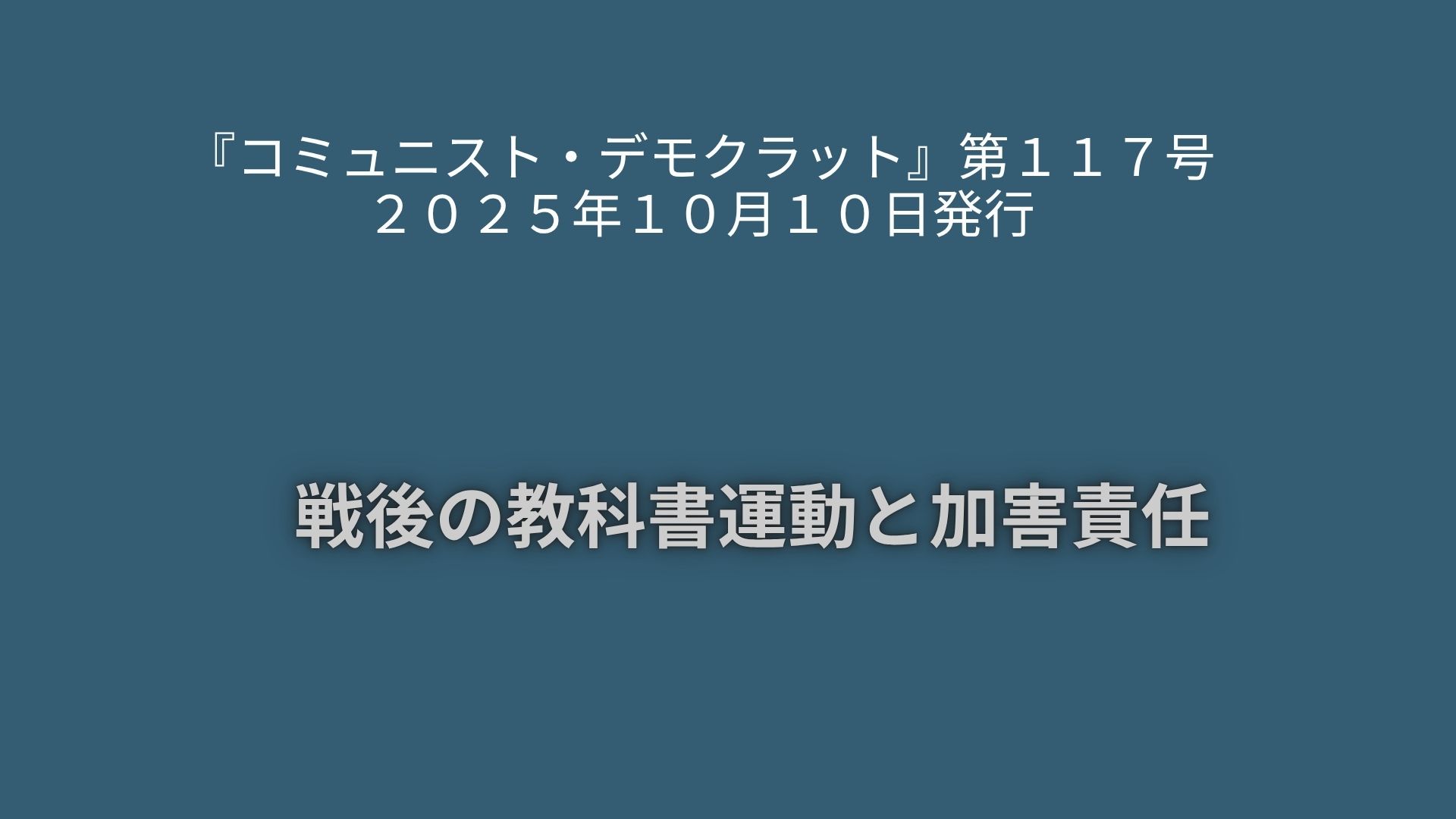教科書運動は、戦後一貫して加害の事実を消し去ろうとする右派に対して、教科書に日本の加害の歴史と戦争責任を記述させる闘いであった。
教科書の加害削除と闘った家永教科書裁判
加害記述を巡る右派との闘いは、朝鮮戦争への日本の加担と日米安保条約の締結、日本の再軍備を背景にして、右派が一斉に教科書の加害記述を攻撃したことに始まる。文部省は、南京大虐殺をはじめアジアでの侵略戦争を抹殺する検定意見をつけた。日本が再侵略の欲望を高めたとき、教科書での加害記述は削除されていったのである。それと果敢に闘ったのが家永教科書裁判であった。家永教科書裁判(1965年第1次提訴)は、文部省の検定介入を真っ向から批判し続け、第3次訴訟(1984年提訴)では日本の加害記述の削除を問う裁判へと発展した。家永教科書裁判はベトナム反戦闘争と結びつき、教科書への原爆や空襲の記述を充実させただけでなく、70年代には韓国併合や強制連行など加害責任を次々と記述させる力となった。
80年代に入ると文部省の検定圧力が強まり、「侵略」を「進出」に書き換えさせた、いわゆる「書かせる検定」問題が起こった。中曽根首相の日米軍事同盟強化と軌を一にしていた。これには中国や韓国などの日本の侵略を受けたアジア各地から激しい抗議が起こり国際問題に発展した。日本政府は検定基準に「近隣諸国条項(近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮)」を認めざるをえなかった。教科書への加害記述は国際公約となったのである。
アジアの被害者の訴えと新たな教科書運動
91年に金学順さんが日本軍「慰安婦」犠牲者として名乗り出て、公然と日本政府に謝罪と賠償を求める運動に立ち上がった。日本軍「慰安婦」問題だけでなく、731部隊犠牲者、住民虐殺犠牲者、遺棄毒ガス犠牲者、無差別爆撃犠牲者たちが次々と戦後補償裁判に立ち上がり、日本の加害責任を厳しく追及した。93年には「河野談話」、95年には「村山談話」が出された。95年度検定中学校教科書には全社で日本軍「慰安婦」問題を記述することとなった。
右派はすぐさま猛烈な巻き返しを始める。自民党内では、93年に「歴史・検討委員会」ができ、97年には「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」(教科書議連)が発足した。同年には右派教科書作りを推進する「新しい歴史教科書をつくる会」(つくる会)と日本会議も発足し、加害記述を「自虐史観」として教科書攻撃する体制を固めた。2001年、文科省は、「つくる会」が編集する扶桑社版歴史教科書(「つくる会」教科書)を検定合格させた。
この動きに対して私たちも「つくる会」教科書の採択に反対する教科書運動をスタートさせた。教科書運動は、文科省の検定意見を不当介入とする裁判闘争から、全国の市町村教育委員会で行われる教科書採択を巡る地域に根を張った市民運動へと広がった。日本の加害責任を追及するアジアの市民運動と連携した。01年、教科書運動の広がりによって「つくる会」教科書の採択率は、歴史0.4%、公民0.2%に追い込んだが、教科書全体の右傾化が一気に進み、06年には中学校教科書から「慰安婦」記述が消滅してしまった。
安倍政権の教科書介入と右派を抑え込んだ教科書運動
06年、安倍政権は、教育基本法の改悪、教科書検定基準の改悪などによって、教科書そのものの右傾化を一層進ませ、文科省の教科書検定も政府見解を書かせる検定となった。15年の中学校採択は、自民党と日本会議が育鵬社(「つくる会」教科書の後継)を全面的にバックアップする採択戦となった。この年、育鵬社は歴史約6.2%、公民約5.7%まで採択を伸ばした。とりわけ大阪では5市で採択を許すことになった。
大阪では、15年の育鵬社大量採択直後から教科書運動の巻き返しが始まった。大阪市では育鵬社採択についてフジ住宅による教科書アンケートの水増しを運動側が暴きだし反撃した。「教育勅語」を日常的に教えようとする森友学園の小学校設置を阻止する闘いも加わった。そして20年中学校教科書採択では、右派の動きを封じ込め育鵬社を激減させることに成功した。
加害責任を教える教科書と教育を
日本軍「慰安婦」をはじめとする日本の侵略戦争と植民地支配の犠牲者たちは、日本政府による謝罪と補償を求めると同時に、日本の歴史教育で加害の事実を子どもたちに伝えることを求めている。私たちはこのことを忘れてはならない。右派教科書を後退させたものの、教科書での加害責任の記述は減り続けている。加害記述の復活に向けて闘いはまだ道半ばである。
(教員 G)