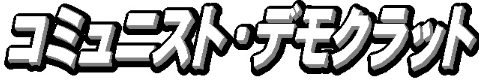――連載にあたって――
レーニンの『帝国主義論』を復活させよう
(1) われわれは、「途上国収奪の定量的分析」に続いて、現代帝国主義に関する世界のマルクス主義者による研究を紹介していく。
現代帝国主義は、マルクス・レーニン主義の理論的・イデオロギーをめぐる左右の偏向の集中点である。右からの現代帝国主義否定論は、随分以前から、社会民主主義化した世界の一部共産党によって取り入れられた。世界は無性格な「独立主権国家の機械的集合体」からなるとされ、ブルジョア政治学・国際関係論に屈服した。
しかし、ソ連崩壊後、帝国主義否定論は、左からも含めて非共産党左派、トロツキズム諸派から、旧親ソ派共産党の一部にまで一気に広がった。共産主義者なら当然であったレーニンの『帝国主義論』や『民族・植民地問題』は、否定されるか、全く別物に歪曲された。戦後、国際共産主義運動の綱領的見解であった、レーニン以来の国際情勢における「4大矛盾論」(資本主義と社会主義との体制間矛盾、帝国主義と新興・途上諸国の矛盾、帝国主義間矛盾、先進国の労資の階級矛盾)は否定され、「3大革命勢力(社会主義諸国、民族解放勢力、先進国労働運動)の団結論」も投げ捨てられた。
われわれは、今こそ、レーニン以来積み上げられてきた「4大矛盾論」、「3大革命勢力弾結論」を復活させ、レーニンの『帝国主義論』を、その現実への創造的適用を含め、取り戻すべきだと考える。
(2) かつてレーニンは、帝国主義間戦争(第一次世界大戦)を支持した第二インタナショナルの裏切りを糾弾するために、その理論的基礎として『帝国主義論』を執筆した。
今日のわれわれも、一部左翼・共産主義運動の実践的誤りに直面している。現代帝国主義戦争、すなわちウクライナ戦争、パレスチナ大虐殺戦争、対中戦争を、米帝主導の「三正面戦争」として捉えないのである。ウクライナ戦争を米・NATO帝国主義による「代理戦争」と捉えず、ロシア‐ウクライナの二国間の「帝国主義間戦争」にねじ曲げる。ガザ大虐殺戦争、直近のイラン侵略を単にイスラエルの暴走に矮小化し、米帝国主義の中東・石油覇権戦略、さらにはロシアや中国を封じ込める「ユーラシア戦略」と捉えない。米帝と西側帝国主義による社会主義中国に対する「体制間戦争」を「帝国主義間戦争」に歪曲する、等々。
これら現代帝国主義戦争に対する階級的誤りは、米帝国主義が戦略的主敵であることを否定すること、中国やロシアやイランを「独裁国家」「権威主義国家」とするブルジョア自由主義への転落、今や全ての国が帝国主義国になったという「帝国主義ピラミッド」論、帝国主義による途上国収奪は存在しないという「植民地主義消滅論」、BRICS·SCO(上海協力機構)をG7帝国主義と同様の「帝国主義同盟」と糾弾すること、世界を「4大矛盾」で捉えることは誤りで、「資本と労働の矛盾」から捉えるべきだ、等々。まさに、「第二インタナショナルの崩壊」を彷彿とさせる状況だ。
トロツキスト諸派やアナーキスト、左翼の顔をした「リベラル左翼」も、これら一部左翼・共産主義者の誤りに同調する。かつて反グローバリズムの論客であったウィリアム・ロビンソンは、世界は帝国主義ではなく「グローバル資本主義」に変容し、国家の役割は縮小し、「超国籍ブルジョアジー」と「超国籍プロレタリアート」に分裂し、「両者の間の階級闘争が基本矛盾になった」「反帝主義者は階級問題を南北問題にすり替えている」と批判する。特に彼は、今回紹介するビジェイ・プラシャドなど途上国マルクス主義者を憎悪し、「反帝国主義左翼」を「愚か者の社会主義」と糾弾し、米帝・西側帝国主義主敵論を「キャンピズム」(陣営主義)と茶化す。米帝を倒しても何にもならないと屁理屈をこね、米帝免罪論を公然と主張する。
新自由主義批判で有名で、邦訳本も多数あるデヴィッド・ハーヴェイは、帝国主義による途上国収奪を否定し、「帝国主義の時代は終わった」「2世紀以上にわたる東から西への富の歴史的流出は、過去30年間でほとんど逆転した」と主張する。パトリック・ボンドは、米帝批判ではなく、「亜帝国主義」概念を武器に中国・ロシア批判、BRICS批判に執念を燃やす。
(3) 連載の最初は、インド出身の共産主義者ビジェイ・プラシャドが率いる「トリコンチネンタル社会調査研究所」の集団労作『ハイパー帝国主義:危険な退廃的新段階』である。2024年1月に発表された。途上国マルクス主義者の帝国主義研究では第一級のものだ。基本的にわれわれの見解と一する部分が多く、読者の皆さんにも研究をお薦めしたい。「ハイパー帝国主義論」は183ページに及ぶ大作である。上中下3回に分けて紹介する。
その後、中国やドイツのマルクス主義者の帝国主義研究、米国の独立系社会主義者(マンスリー・レビューなど)の帝国主義研究を順次紹介していく。
(編集局)
*****
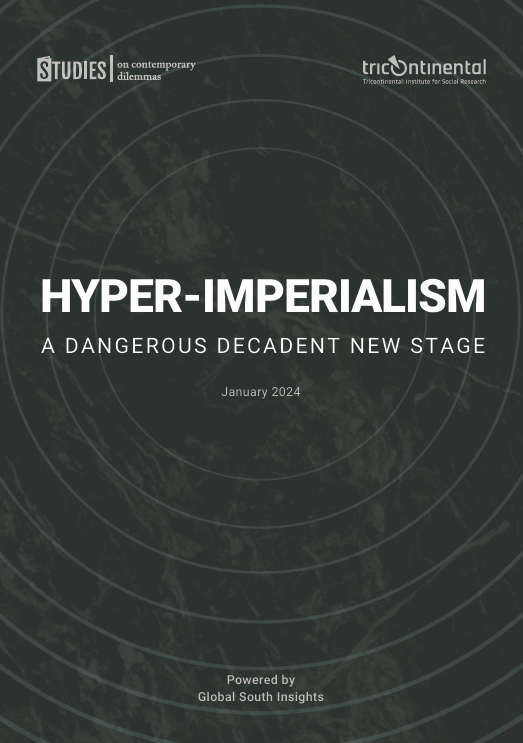
集団労作『ハイパー帝国主義:危険な退廃的新段階』は、以下の7部構成からなる。見解の違いや疑問点は、以下の紹介の中で具体的に指摘したい。なお、本研究を読めばすぐに分かるが、ここで言う「ハイパー帝国主義」とは、帝国主義の諸矛盾を塗り隠し、帝国主義と帝国主義戦争を擁護するカウツキーの「超帝国主義論」の「ウルトラ」(ultra)とは全く違う。「ハイパー」(hyper)とは、異次元の、度を超えたという意味で、米帝主導の西側帝国主義による「三正面戦争」に明らかなように、帝国主義の異常な侵略性と暴力性を表現する概念である。
はじめに
第Ⅰ部 米国主導の完全なグローバル・ノース軍事ブロックの台頭
第Ⅱ部 帝国主義の進化
第Ⅲ部 定義された世界
第Ⅳ部 衰退する西側
第Ⅴ部:世界秩序の変化
エピローグ:信頼できる経済的・政治的代替世界秩序
われわれが本研究を基本的に支持する理由は5つある。第1に、米帝国主義に対する戦略的主敵論に貫かれていることである。「米国主導の軍事ブロック」がキーワードだ。米帝主導の西側帝国主義の「5大覇権」(軍事覇権、政治覇権、ドル・金融覇権、技術覇権、メディア・文化覇権)とその衰退に頻繁に言及される。
第2に、徹底的な反植民地主義、社会主義中国と新興・途上諸国の側からの階級的告発だということである。「はじめに」にある言葉は鮮烈だ。「帝国主義の牙を首筋に感じる人民の闘争」の見地で全体を貫くと言う。新興・途上諸国の民族解放運動に密着する研究者の集団的労作なのである。
第3に、超長期の歴史的視点である。西洋資本主義を生み出した「植民地・半植民地・奴隷制の600年の暴力と略奪の歴史」への糾弾で貫かれていることである。これも先進諸国のマルクス主義者にはない視点だ。
第4に、本研究の唯物論的・弁証法的スタイルである。マルクス主義者が陥りやすい浅薄なやり方、例えば、世界の現実から始めるのではなく、レーニンの『帝国主義論』の5つの指標をなぞるやり方、命題を現実に外面的に当てはめるやり方とは異なることだ。現代帝国主義の侵略的で獰猛な最新の段階のダイナミズムを暴き出し、糾弾する方法の素晴らしさである。「弁証法は実例の総和ではない」と強調したレーニンを思い起こす。
第5に、本研究全体が、今日の侵略し収奪する側である先進諸国の一部の左翼・共産党の許し難い誤りに対する糾弾となっている。例えば、米帝主敵論を否定し、「中国・BRICS帝国主義」に攻撃の矛先を逸らせる米帝免罪論、新興・途上諸国全体が帝国主義に転化したとする「帝国主義ピラミッド論」や「米中帝国主義間矛盾論」、「亜帝国主義論」、もはや植民地は一掃されたとする植民地主義終焉論など。
*原文『Hyper-Imperialism:A Dangerous Decadent New Stage』
https://thetricontinental.org/studies-on-contemporary-dilemmas-4-hyper-imperialism/
[1]はじめに:米帝覇権の衰退を侵略と軍事覇権で巻き返す
(1) 「はじめに」で、著者らは2つのことを論じる。一つは本研究の基本的枠組み、もう一つは、ハイパー帝国主義段階がいつ始まったかである。
基本的枠組みについては、米帝国主義が、社会主義中国とグローバル・サウスの急激な台頭に対して衰退し始めたことを、現代帝国主義のダイナミズムの原動力とする。米国が2014年に購買力平価で中国に追い抜かれる、設備投資の減少、経済の金融化、製造業の優位性の喪失、政治的分裂、中国とロシアの体制崩壊の失敗、等々。しかし、その衰退はまだ始まったばかりで、製造業覇権は失ったが、技術的覇権はまだ残り、ドル・金融覇権は揺らいでいるがまだ初期段階にある。だからこそ、米帝は、今のうちに、経済的衰退を軍事力で巻き返そうとしているという理解だ。
その上で、米帝の「5大覇権」のうち衰退した生産力・技術覇権、ドル・金融覇権を前にして、軍事覇権(「軍隊の筋肉を鍛え」)とメディア・文化覇権(「真実の支配」)、一言すれば、「文化と戦争」が衰退した帝国主義の巻き返し戦略の柱と結論づける。
(2) 「はじめに」は、ハイパー帝国主義段階への転化を、米帝主導の西側帝国主義の侵略性と凶暴さを露わにした2022~23年頃、つまり22年のウクライナ戦争、23年のイスラエルのガザ大虐殺戦争をその指標とすると説く。この頃に「帝国主義体制は質的に変化した」「新たな段階であるハイパー帝国主義へ変貌し始めた」「米国が、他のすべての帝国主義諸国に対する経済的、政治的、軍事的従属を完了し、統合され、軍事的に集中した帝国主義ブロックが形成された」と。
一方で、第Ⅱ部「帝国主義の進化」では、2008~22年を新段階の「移行期」(A Transition)と規定する。両者の関係をどう見るか?われわれの理解はこうだ。つまり、リーマンショック以降、一方での中国とグローバル・サウスの台頭、他方での米帝と西側帝国主義の衰退と退廃が諸矛盾を激化させた(移行期)。その帝国主義的巻き返しとして、2022年以降、「米国主導の軍事ブロック」による「三正面戦争」という帝国主義の超危険な段階に移行した。新段階は移行期を含めて2008年から始まるが、その質的変貌の頂点は2022年以降である。
当然、侵略され収奪される新興・途上諸国は、この帝国主義の暴力的変貌を肌身で感じる。その恐怖をこう表現する。「その痙攣のような力は、米国の軍国主義の下で暮らす何百万人ものコンゴ人、パレスチナ人、ソマリア人、シリア人、イエメン人にも感じられ、彼らの頭は、突然の物音に本能的にピクピクと反応する」と。この恐怖を感じ取ろうとしない先進国のマルクス主義者とは、いったいどんなマルクス主義であろうか。
[2]第Ⅰ部:完成された米国主導のグローバル・ノース軍事ブロックの台頭
(1) 本研究は、「米国主導の軍事ブロック」(US-Led Global North Military Bloc)の分析に帰着する。第Ⅰ部では、49カ国からなるこの軍事・政治・経済の統合ブロックを「グローバル・ノース」(以下、GN)と規定し、その「軍事ブロック」の「変化と統合」のダイナミズムを全面的に捉える。ソ連崩壊後の30年の「内部変化」が2つあったとする。第1は、NATOの東方拡大によるこの「軍事ブロック」の拡大。第2は、西欧資本主義諸国の対米従属の完成である。
次の規定は重要だ。すなわち、この「『米国主導の軍事ブロック』の中心はNATO」であり、「このブロックには、日本、オーストラリア、イスラエル、ニュージーランド、グローバル・サウス3カ国、そしてNATOに加盟していない数少ないヨーロッパ諸国も含まれている」とブロックの範囲を確定した上で、この「米国主導の軍事ブロックは世界で唯一のブロックであり、中央司令部を持つ事実上の軍事同盟である。この種のブロックは他にない」と言う。本研究は、「中国帝国主義論」や、米中矛盾を「米中覇権争い」とする米・NATO帝国主義を免罪する謬論をきっぱりと否定する。中国主導のBRICSやSCOは軍事ブロックではない。本研究は「GNとは対照的に、GSはブロックでも軍事ブロックでもないことは明らかだ」と主張する。
(2) その後、この「軍事ブロック」を、「軍事費」「米英の軍事基地」「米英の軍事侵攻、介入、『展開』」の順に展開する。国際共産党の一部が、米帝国主義を戦略敵と捉えず、露骨に免罪する議論がどれほど馬鹿げたものかを、図表を交えて詳細に分析し、全面的に暴露する。本研究の圧巻部分だ。
結論は鋭い。われわれと同じ「米帝主敵論」である。「すべての国の、とりわけ世界の暗い国々(途上諸国)の労働者階級にとって、絶対的な中心的危険(the absolute central danger)は、米国主導の帝国主義陣営にある」。そして、一部の左翼・共産主義者が主張する「亜帝国主義論」も切り捨てる。「客観的には、亜帝国主義や非西洋帝国主義勢力など存在しない(そのような概念は、事実的な現実を曇らせる主観的な欺瞞である)」と。
[3]第Ⅱ部:帝国主義の進化
(1) 第Ⅱ部では、「帝国主義の新たな段階」を論じる。帝国主義はソ連崩壊後に形成された「米国一極秩序」が、2008年のリーマンショックから22年のウクライナ戦争の間に衰退・弱体化し、「グローバル帝国主義の量的・質的変化が固まった」。本研究が描く「新しい段階」と特徴は以下の通りである。
――中国の台頭。GSの成長がGNの成長を上回る。
――米国の低成長。米国による中国・BRICSの台頭の抑制。
――米国による制裁、外貨準備の強奪。ハイブリッド戦争。
――西側諸国による中露との対峙。
――帝国主義の軍国主義的進化。相対的な経済的・政治的衰退を相殺するための軍事的優位への依存。個々の資本家やグループの利益、短期的な経済的損失を二の次とする軍事力最優先。
――ドル覇権、金融化、技術力による金融取引優先の資本主義的蓄積。
――新世代の高度なソーシャルメディアに基づく「ソフトパワー」インフラの強化。米国軍産デジタル複合体。
――帝国主義間矛盾の非対立的かつ二次的な性格。ドイツ、日本、フランス、その他すべての帝国主義国の利益の米国への従属。
――GSの新しい多国主義機関、代替開発資金調達モデル。一帯一路構想(BRI)、BRICSへの参加の高まり。国連加盟国の80%近くがBRIに参加、世界人口の約64%、世界のGDP(購買力平価)の52%を占める。BRICS10カ国は世界人口の45.5%、世界GDP(購買力平価)の35.6%を占めている。これに対し、G7は世界人口の10%、世界GDP(購買力平価)の30.4%。
――米欧の経済的、政治的、道徳的リーダーシップの信頼喪失。脱ドル化。
――ヨーロッパ人とその子孫である白人入植者による植民地国家が世界情勢を支配することに対して、600年以ぶりに、経済的にも政治的にも信頼できる代替案が登場した。第一に、中国が率いる社会主義グループである。
第二に、グローバル・サウスから台頭してきた、国家主権、経済的近代化、多国間主義への熱望の高まりである。
(2) このような新段階の特徴を踏まえて、著者らは、「米国主導の軍事ブロック」は中露の分割・解体、属国化、非核化という地政学戦略を掲げていると言う。最前線攻撃対象には中国、ロシア、朝鮮民主主義人民共和国の3つの核保有国、「潜在的核保有国」と決めつけられたイランが含まれる。シリア、ベネズエラ、キューバ、ベラルーシも政権交代の当面の標的だ。
本研究は、一方で、「米国主導の軍事ブロック」を前にして、GSの弱さを強調する。多様で異質でブロックを形成しておらず、イデオロギー的にもバラバラで軍事同盟も結んでいない。だから、「世界は非常に困難で危険な瞬間に直面している」と危機感を露わにする。
だが他方で、植民地の歴史が生み出した強さも指摘する。「彼らは何百年もの間、グローバル・ノースによる植民地的、半植民地的な虐待を受け」「歴史を共有している」「グローバル・サウス諸国間で共有されるアイデンティティの強い意識は、簡単に否定することはできない」と。
本研究は、ここで決定的に重要な指摘をする。植民地主義的迫害に対する「民族主権」(national sovereignty)こそが、「深く民主的」であり、「人民の生活を向上させる」ものであり、それが故に、「社会主義への必要な一歩でもある」(a necessary step towards socialism)と。民族主権は途上国の民主主義運動、社会主義運動への前進に不可欠だと言うのである。当然だ。絶えず「米帝主導の軍事ブロック」に侵略され、制裁と政権転覆にさらされる限り、つまり民族独立なしに革命は起こせないからだ。侵略し収奪する帝国主義の左翼・共産党の一部左翼主義者は、「民族独立より社会主義革命だ」と暴言を吐くが、このような浅はかな考えは、帝国主義の軍事介入に苦しんだことのない、侵略する側にいるからこそ言えるのである。
(3) 第Ⅱ部の最後は、現代帝国主義から最新の「ハイパー帝国主義」段階の歴史を辿り、それぞれの時代の特徴を解明することである。
① 「帝国主義の前史」:筆者ら途上国マルクス主義者は、通常、先進国マルクス主義者がやるように、レーニンの『帝国主義論』や第二次世界大戦後から始めるのではなく、「帝国主義の前史」、すなわち資本主義そのものを生み出した1415年以降の大航海時代、その植民地主義、奴隷制による血まみれの資本の創世記(マルクスの本源的蓄積)から始める。その後、現代帝国主義の100年の本史を区分する。1890~1916、1917~1939、1940~1945の3つの時代である。
② 「ハイパー帝国主義」段階:そして最新段階に移る。筆者らのオリジナリティは、2008~22年の14年間の「移行期」(A Transition)を詳細に分析していることだ。一言すれば、社会主義中国の台頭と、米帝一極支配の崩壊、西側帝国主義の衰退・没落である。「移行期」は2007~08年のグローバル金融恐慌=「第三次世界恐慌」に始まる。ところが、社会主義中国は、この恐慌とは無縁に発展する。これを帝国主義陣営が恐れたのだ。
この「移行期」に米国主導の西側帝国主義を襲った政治的・経済的・社会的諸矛盾、「巨大な諸転換」(major shifts)が2022~23年以降の今日の「三正面戦争」に代表される「米国主導の軍事ブロック」の異常な侵略性・暴力性を生み出す。著者らが指摘した「移行期」の諸矛盾は10点だ。
1.最も重要な変化は、購買力平価(PPP)で中国が世界最大の経済大国となった。2.同じくGSがPPP測定で世界GDPの40%から60%へ拡大した。
3.第三次世界恐慌により、GDP成長率はさらに低下した。
4.欧州と日本の資本は、資本市場の急速な変化によって加速度的に「脱国有化」(民営化)した。
5.習近平政権誕生により、中国社会主義は自らを強化し、新たな「中国のゴルバチョフ」を期待した西側諸国は完全に失敗した。
6.NATO諸国は世界で軍事介入したが、アフガニスタン、イラク、さらにはシリアなどで敗北した。
7.NATOを東欧に拡大し、ウクライナを代理人としてロシア支配の中心に据えるという米国の決定は、核保有国同士の重大な軍事衝突を招いた。
8.経済的・政治的覇権の相対化衰退に直面した米国は、制裁、司法戦争(国際法の悪用)、関税、外貨準備の没収などの手段を大々的に拡大し始めた。
9.中国の技術進歩を阻止しようと、米国は関税と保護主義を使い、新冷戦を始めた。
10.米支配層は、軍事覇権を利用して中国を封じ込め始めた。ロシアを「失った」ため、米国はユーラシア大陸を永久に従属させるという歴史的使命をに注力している。
(続く)