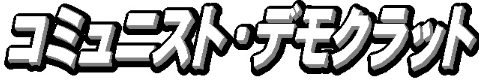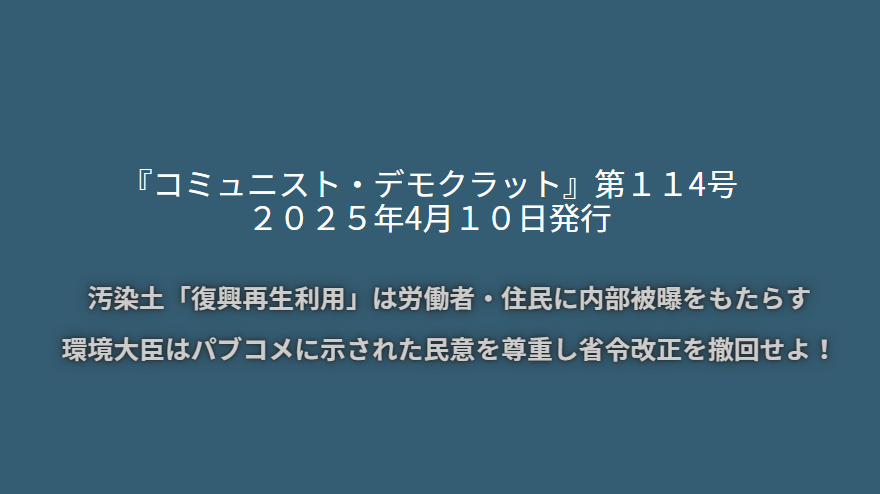3月28日、環境省は汚染土「復興再生利用」の省令改正(案)パブコメに20万7850件の意見が寄せられたと発表した。一方で「句読点、記号、改行も含め一字一句完全に一致した御意見を1件として整理した場合の意見数は8277件であった」としている。「意見の概要」で見ると賛成意見は7件程度である。それ以外は反対や環境省の進め方に異議、疑問を呈するものがほとんどだ。同一意見は1件と数える環境省のまとめでも圧倒的に市民は汚染土「復興再生利用」に賛成していない。
それにもかかわらず、環境省は強引に同日省令公布、4月1日から施行した。大熊・双葉両町にまたがる中間貯蔵施設に埋設されている膨大な量の汚染土(除去土壌)のうち8000ベクレル/㎏以下の汚染土を「復興再生利用」という新造語でごまかし、実質的に最終処分を行うつもりだ。現行法で決められているクリアランスレベル(放射能汚染廃棄物としてみなさず制限なく再利用できる基準)である100ベクレル/㎏を事実上80倍にも緩め、廃棄物とは区別されていた土壌にまでそれを適用するという暴挙である。
放射能ばらまきに反対する闘いは、全国の自治体や地域の闘いで止める局面に入った。各地の運動強化で放射能ばらまきを止めよう。
異例の反対意見数をコピペ問題に矮小化しようとした環境省
パブコメ結果の発表当日、福島民友は「政府関係者によると、少数市民がウェブサイトから大量に送った可能性がある」と報じた。環境省の意図的なリークだ。報道発表で「19万9573件(約96%)はこれら8277件の御意見と一字一句完全に一致した御意見でした」と報告、浅尾環境大臣は「行政事務の適正な執行の妨げになり得る」とまで述べ、反対意見数の多さを、SNS上での投稿呼び掛けや、「コピペ」問題に矮小化する意図を露わにした。
しかし今回の省令改正(案)は、法律専門家でも理解に苦しむような極めてわかりにくい形で提起され、また放射線審議会に諮問しながら未答申であるにも関わらず省令改正(案)としてパブコメにかけ「手続き上の瑕疵」さえ指摘されていた。内容の理解と反論が困難な多くの住民、市民にとって、参考とする他者の意見と同感なら同じ投稿をすることは、適正な行為だ。環境大臣はパブコメで意見を表明したい、という国民の強い意思を受け止めるべきだ。
対象は福島県を含む「全国」 福島県内でも「復興再生利用」名目で処分が可能に
今回の省令改正では復興再生利用の対象が「全国」となっている。これまで、環境省は「除去土壌の再生利用」の必要性として、「大熊、双葉両町との約束で、中間貯蔵施設内の除去土壌は30年後の2045年までに全て県外処分が必要」(下線は筆者、以下同)、「県外処分のためには減容化が必要」、「処分には再生利用も含まれる」と説明してきた。そうであれば「復興再生利用」の対象は「福島県を除く全国」となるべきものである。「処分に再生利用が含まれる」ならば、「復興再生利用」は「処分」そのものであり、30年後までに「全て県外処分」という説明と明らかに矛盾する。論理的にも矛盾する強引な施策は、中間貯蔵施設に指定された地域の地権者をはじめとして原発事故被害者を愚弄するものだ。
福島原発事故で発生した大量の汚染廃棄物をどのように処分すべきか。原理原則に立ち返って方針を改めるべきである。何よりもまず求められるのは原発事故直後に緊急対応的に制定された汚染対処特措法の抜本的見直しの国会審議だ。さらに放射性物質に関する環境基準の制定、現行のクリアランスレベルに基づく汚染廃棄物の集中管理、隔離、モニタリング、環境基本法に則り「発生者責任」に基づく必要な措置を実施することだ。
重要な点があいまいにされた無責任極まりないガイドライン
今回のパブコメで参考資料として挙げられた「ガイドライン(案)」は改訂され正式なものとなった。しかし、IAEA(国際原子力機関)への説明で強調された「管理された再利用」の柱ともいうべき重要な点が意図的に曖昧にされ、管理責任が不明になる極めて無責任な内容のまま決定された。
先ず、再生利用事業実施者について、これまで環境省が説明して来た「公共事業等」という説明が「公共事業又は実施主体及び責任体制が明確であり、かつ、継続的かつ安定的に行われる事業において行うこと」へと拡張された。近年、公共事業を民営化する動きが推進されている(PFI)。PFI化された自治体の公園などの盛土に使用され、この請負企業が倒産、資産譲渡などを繰り返す過程で管理責任が曖昧になる可能性がある。100年単位の長期にわたり管理する必要があるが、この終了時期については「復興再生利用の終了の考え方(どのような状態になった場合、あるいはどのような期間が経った場合に、(中略)、様々な措置を終了できるか)については、今後環境省において整理を行う」と曖昧なまま残された。
汚染土再利用はセシウム微小粉塵を発生させ、労働者・周辺住民に内部被曝をもたらす
「除去土壌の復興再生利用」は、その全工程でセシウム等放射能を含む微小粉塵を広範囲に飛散させる。特に重要なのは住民の粉塵吸入リスクが施工完了後も長期にわたり続くことだ。8000ベクレル/㎏の土壌がクリアランスレベルに減衰するまでに190年かかる。日本国中どこにおいても100年単位の長期間にわたり、洪水、土砂崩れなどの自然災害から免れることができると想定するのは非現実的だ。一旦大規模な洪水、土砂崩れなどが起これば、覆土もろとも汚染土は広い範囲に流出する。汚染土が乾燥すれば微小粉塵が大気中に舞い上がり拡散する。
微小粉塵を吸入すると肺の奥の肺胞に長期間沈着し、被曝リスクが極めて高くなる。また微小粉塵やこれよりやや大きな浮遊粒子状物質は大気中を長期に浮遊し続け広範囲に拡散する。施工時のみならず自然災害による汚染土流出は、その工事や対応に携わる労働者だけでなく周辺住民にとっても、内部被曝の危険性が極めて高く危険だ。
環境省・IAEAの狙いは、汚染廃棄物処理基準の大幅緩和
2024年9月、環境省はIAEA専門家会合の最終報告を発表した。この報告では以下のような一文が含まれている。「除去土壌の再生利用に関する先進的な取組から得られた知見は、他国が参考にできる有益なケーススタディである。(中略)国際社会への普及が奨励される」。このことから判る彼らの真の狙いは、今後世界で起こりうる過酷事故の後始末や増加する廃炉処理に際し、汚染廃棄物規制の大幅緩和による被ばく防止対策の大幅コスト削減にある。
事故の後始末でも荒稼ぎする原発独占の暴走を運動の力で止めよう
除染と中間貯蔵施設設置、減容化、再生利用は初めからセットで進められてきた。2011年11月に国立環境研の大迫政浩を理事長として環境放射能除染学会が設立された。ほとんど同時期に東電が発起人となり「除染・廃棄物技術協議会」(後に「除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合」へ組織替え)を設立した。「学会」「技術協議会」とはいうものの、実態は除染とその後の減容化、再生利用を新たなビジネス・チャンスと捉えた原発独占資本、原発ゼネコン、大手産廃業がリードし、そこに御用学者が群がり汚染土処理、減容化技術開発で暴利を独占し分け合う「談合組織」だ。
環境省はこれら「独占合議体」からの技術提案に予算を湯水のように投じ、汚染廃棄物焼却炉と8000ベクレル基準に土壌を分類する分級施設による分別、埋め立てを実施した。環境省は中間貯蔵施設関連だけですでに2.2兆円、これまでの除染費用の約半分が、こうした焼却炉、減容化処理施設のために使われている。
今回の省令改正により、今後実施される「復興再生利用」には膨大な予算がかかる。環境省はその概算すら示していない。単純に考えてもこれまでと同程度2.2兆円程度はかかるだろう。
さらに今回の省令改正で決められた「復興再生利用」の対象は、新聞等で説明されているような、中間貯蔵施設内に埋設済みの3/4の汚染土(8000ベクレル/㎏以下)だけが対象ではない。残りの1/4の高濃度汚染土壌や、廃棄物焼却で生じた焼却灰(8000ベクレル/㎏超~10万ベクレル/㎏以下)についても、様々な手法での減容化実験がすでに終了している。究極は7億ベクレル/㎏という超高濃度の灰がドラム缶にして25本程度残るだけで、それ以外は全て「再生利用」としてばらまく計画まである。
現に始まろうとしている「復興再生利用」を止めると同時に、この高濃度汚染物の減容化を問題にして止めなければ、環境省は粛々と中間貯蔵施設の中で「独占合議体」の言い値で究極の減容化処理を実施するだろう。これらの費用はいずれ電気代への上乗せ、あるいは税金という形で市民、人民大衆に付け回される。いくらの予算をかけてどこまで再生利用するのか、それとも再生利用ではなく、原理原則に則り集中保管するのか、これは技術の問題ではなく政治の問題だ。
環境省は環境を守り住民と人民大衆の健康と命、地権者や原発事故被害者の利益のためではなく、ごく一部の原発関連独占体の法外な、ぼろ儲けを隠し合法化する「イチジクの葉」に成り下がっている。危険な汚染土再利用を止め、放射能ばらまきをストップさせることは、住民・人民大衆が政治の主導権を取り戻す闘いそのものである。
(A)