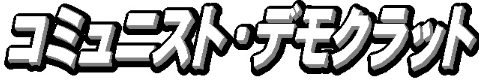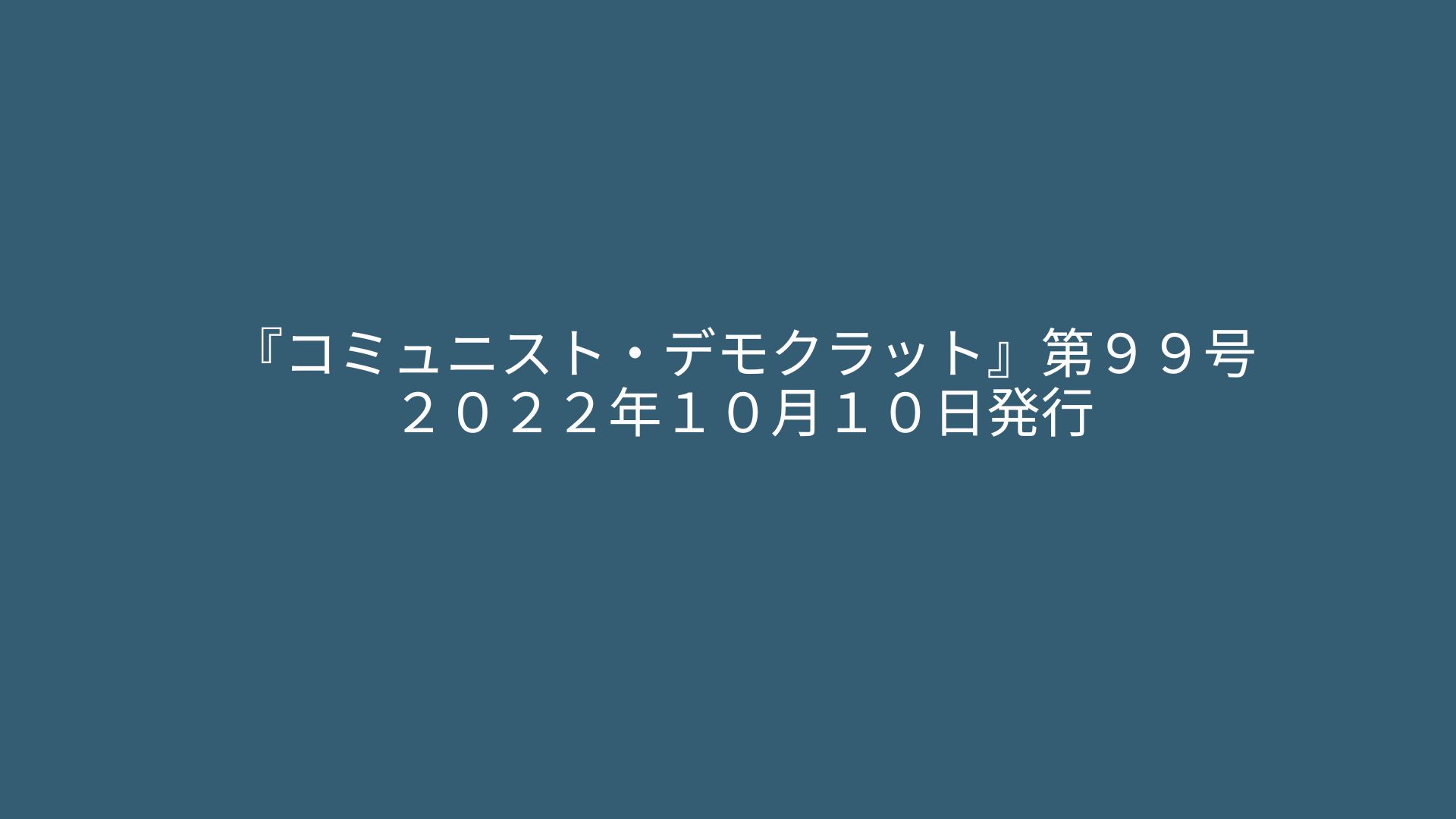○ 中国との平和共存、友好・協力政策への転換を
○「中国脅威論」を批判し、反中・嫌中意識を変えていこう
[1] 「台湾有事」策動の危険ーー対中軍備増強を本格化し始めた岸田政権
(1) 9月29日の日中国交正常化50年は、米国が「台湾有事」で対中軍事挑発をエスカレートさせ、日本政府もまた米に全面加担して対中挑発と参戦準備を本格的に進め始める中で迎えた。
「台湾有事」策動は、米バイデン政権の対中軍事挑発、中国破壊活動の目下の集中点である。それはアジアと世界の平和に対する最大の脅威となっている。
重大な転換点となったのは、8月2日のペロシ米下院議長の訪台だ。それは、「台湾有事」をめぐる軍事的緊張と米中対立を一気に新しい危険な段階に引き上げた。バイデン政権は、空母打撃群でペロシ搭乗機を護衛し、中国に対して軍事的威嚇を行った。公然たる軍事挑発であり、一触即発の危険極まりない状況を作り出した。中国側は自制したが、軍事演習や台湾への制裁で対抗措置をとったのは正当な行為であった。
米バイデン政権の異常なまでの好戦性、侵略性は、トランプ政権の比ではない。バイデンはウクライナでの「代理戦争」「ハイブリッド戦争」をエスカレートしながら、「台湾有事」で対中戦争挑発を加速させ、さらに「朝鮮半島有事」にまで手を出し始めた。米軍が3正面で戦争策動をエスカレートさせるのはかつてないことだ。
現在の最大の攻撃対象は、本来の主敵である社会主義中国である。ペロシ訪台だけでなく、南シナ海と台湾周辺での対中軍事威嚇・挑発を繰り返している。9月2日には、対艦ミサイル、空対空ミサイルなど総額11億ドルもの台湾への武器売却を決定した。米政府は、口先では「一つの中国」政策は守ると繰り返しているが、実際は全く正反対の政策で、「台湾独立」=中国分裂策動を強めているのだ。
(2) さらに危険なのは、米議会で審議が始まった「台湾政策法案」である。9月14日には米下院外交委員会で可決された。それは、①台湾を非NATOの同盟国並みに扱う、②他の外国政府と同様の外交待遇で外交特権を付与、③軍事援助拡大、攻撃兵器の解禁、軍事同盟追求、④軍事費の大幅増額を要求、等々と事実上台湾「独立」を認め、中国国家を分裂させるに等しいものだ。自衛隊の南西諸島の軍事要塞化と結合させ、「日米台同盟」を構築して、格段に戦争の危険性を高める。この法案が可決されれば、「一つの中国」原則は根底から破壊され、対中戦争の危険は一気に高まる。
だが法案の内容は着々と実行に移されている。米台間の共同作戦計画が練られ、米軍特殊作戦部隊と海兵隊部隊の台湾軍との訓練がすでに行われている。台湾政策法はその制度化と公然化を狙うものだ。
(3) 岸田政権は、バイデンの「台湾有事」策動と一体化して、これに全面的に加担する対中軍備の大増強を進め、日米共同作戦計画を具体化し始めている。防衛省は「敵基地攻撃能力」保有のために、長射程ミサイル(スタンド・オフ・ミサイル)1500発以上の大量配備、総合ミサイル防空能力など軍事力の抜本的増強を来年度政府予算で計上する方針だ。すでに政府は、「防衛力の5年以内の抜本的強化」(首相所信表明)方針に基づいて年額11兆円を超える軍事費2倍化、「防衛3文書」(国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防)の年内策定に動き始めている。
さらに2015年の安保関連法制(戦争法)が、「台湾有事」の際に日本が自動的に参戦する仕掛けであること、その際、南西諸島が最重要の出撃拠点となることが明らかとなった。最近、政府が発表した「台湾有事」を想定した南西諸島での住民避難シェルターの検討は、計画を進めるためのものだ。南西諸島の軍事要塞化と辺野古基地建設強行は、沖縄と島嶼地域だけでなく日本全土をバマ政権が2011年11月に打ち出した、対中戦争に巻き込む危険性を高めている。
米国が主導し、日本政府が全面加担する「台湾有事」策動に断固反対し、自衛隊の対中戦争先兵化に反対する運動を作り上げていくことが急務である。
[2] 日本こそ日中共同声明の原点に立ち返るべき
(1) 日中関係はこの50年間で一変した。日本国中が沸き立った半世紀前の日中友好、協力・連帯の雰囲気は完全に消え去った。日本政府は対中対決路線を鮮明にし、メディアは反中・嫌中プロパガンダを何の批判も受けることなく野放図に垂れ流している。
9月29日の各紙社説は、今日の日中関係の緊張と困難を作り出したのが中国の「覇権主義」「一方的な現状変更」にあると断じた。読売や産経などの右翼・保守メディアだけではない。朝日や毎日などもまた、表向きは友好を唱えながら、「巨大な隣国の危うさ」(朝日社説)などと中国に責任をなすりつける論を展開した。
政府・メディアだけではない。野党を含む議会政党の圧倒的部分が「中国脅威論」を振りまき、中国敵視ではほぼ完全な翼賛体制がつくられた。とりわけ日本共産党は、中国の「覇権主義」「人権侵害」批判を前面に押し出し、米国と日本の対中包囲・中国敵視の軍備増強に対する批判を行うことさえしなかった。こうして助長される「中国脅威論」が、人民の批判的意識を骨抜きにし、差別・排外主義を植え付け、これをテコにして対中戦争準備・軍備増強が強引に推し進められていることに危機感を抱かずにはいられない。
現在の日中間のあつれきと緊張を作り出しているのは誰か?「一方的現状変更」を行っているのは中国か? メディアが垂れ流す「中国の脅威」は事実なのか? 結論を先取りすれば、これらはすべてウソ、デタラメである。日中関係に緊張を持ちこんでいるのは中国ではない。米日の帝国主義である。米バイデン政権と岸田政権こそが、「力による一方的現状変更」の張本人だ。このことを繰り返し暴き出していく必要がある。
(2) 日本政府こそ、日中共同声明(1972年)の原点に立ち返るべきである。われわれは、日中両国が国交正常化の出発点で確認した諸原則、とくに侵略戦争の反省と「一つの中国」こそが国交正常化の大前提であり、日中関係の基礎であることを強調したい。
第1に、歴史認識と侵略戦争についての反省。「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」(共同声明前文)。
第2は、「一つの中国」原則の確認。日本政府は、中華人民共和国を唯一合法政府として認めた。同時に日華平和条約が存続の意義を失ったと表明して、台湾と断交した。
第3は、中国の日本に対する戦争賠償請求権の放棄。
第4に、平和共存5原則(主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存)および「紛争の平和的解決」「武力・武力による威嚇に訴えないこと」の確認。
第5に、釣魚島(尖閣諸島)問題の「棚上げ」合意。国交正常化交渉に伴う対話の中で、「紛争棚上げ」は両国指導者間の黙契であった。これは平和友好条約時にも確認された。
共同声明に明記されたように、天皇制日本帝国主義の戦争責任に対する痛切な反省なしに、日中国交正常化は実現しなかった。それは日本国憲法の戦争放棄、侵略の被害を受けた中国とアジア諸国人民に対する「不戦の誓い」と一体のものだ。日本政府がこのことを明確にし、日中の平和共存と友好協力、「紛争の平和的解決」「武力による威嚇に訴えない」ことを中国と中国人民に約束したからこそ、中国は対日賠償請求を放棄したのである。
平和共存5原則と「紛争の平和的解決」は、6年後の日中平和友好条約の締結で法的拘束力を持った。その意義を改めて確認する必要がある。今日、日本が締結する「平和友好条約」は、この日中平和友好条約ただ一つである。
日本政府が進める「台湾有事」への加担の具体化、南西諸島への自衛隊配備、大量のミサイル配備等々の対中軍備増強は、これ自体が「平和的手段による解決」に真っ向から反する。岸田政権は、日中国交正常化での日中間の約束、双方が確認した諸原則を投げ捨てるのではなく、日中共同声明・日中平和友好条約の原則・精神に立ち返るべきである。
[3]「力による一方的な現状変更」の張本人は日米の帝国主義
(1) 米国と日本をはじめ西側諸国と主要メディアは、ペロシ訪台に対する軍事演習やミサイル発射などの中国の対抗措置に対して、「力による現状変更の試み」などと一斉に騒ぎ立てた。これまでも、釣魚島問題、南シナ海問題、空母就航など、事あるごとに「中国の大軍拡」などと中国を非難し、一方的に責任を押しつけてきた。だが「力による一方的現状変更」を仕掛けてきたのは米帝国主義であり、これに付き従ってきた日本帝国主義である。
米国が明確に対中対決戦略に転換し始めたのは中国との対決を強く念頭に置いた軍事外交政策=「アジア・ピボット」戦略以降である。さらにトランプ政権は2017年12月、米国の軍事戦略の基本を、従来の対テロ戦略から明確に中国とロシアを敵にするものに変える「国家安全保障戦略」を打ち出した。ところがバイデンは主敵を中国一国に絞ると同時に、帝国主義同盟によって中国に対抗する戦略転換を行った。台湾民進党の蔡英文へのテコ入れを強めながら、日米、米韓、日米豪印などを総動員して対中戦争挑発を強めている。
米国の対中戦略の相次ぐ転換は、2010年に中国がGDPで日本を追い抜いて世界第2位になったこと、さらに2012年11月、習近平指導部が誕生して社会主義路線を強化し始めたことが直接的な要因である。米帝一極支配と帝国主義の覇権主義体制が掘り崩されることへの危機感が根底にあった。米を先頭とする帝国主義体制は、自らの軍事・政治・貿易・ドル金融、等々の覇権体制の維持と巻き返しのために、対中包囲で社会主義中国に打撃を与える戦略を基本に据えたのだ。
(2) 日本の対中軍事外交政策が、はっきりと中国敵視=対決路線に転じたのも、2010年代以降である。日中国交正常化から2000年代までは、歴史認識問題や靖国参拝で対立が生じたが、日本の基本戦略は中国の経済発展を促すことで、WTO加盟等を通じて帝国主義陣営に取り込み、自らの新植民地的発展の足場とすることであった。
日本の対中対決への転換は、民主党野田政権から始まった。まずは漁船衝突事件を最大限に利用し(2010年)、次に尖閣諸島国有化(2012年)で大きく踏み出した。当時の野田政権は、極右政治家と自民党が領土問題で攻勢をかけた結果「国有化」を強いられた。それは、日中共同声明と日中平和友好条約の交渉時の「棚上げ」合意を一方的に反故にするものであり、中国側が激しく非難したのは当然であった。
だが軍事面を軸に全面的な対中対決へと転じたのは、安倍政権である。安倍は、特定秘密保護法制定(2013年)、集団的自衛権容認(2014年)、安保関連法案(戦争法)強行(2015年)など一連の軍国主義諸法案を一挙に推し進めた。本格的な対中軍備増強は、ここから始まったのである。当時、安倍は「米の戦争に巻き込まれることは絶対にない」と言い放ち戦争法を強行したが、昨年末には一転「台湾有事は日本有事」と明言した。一連の法的整備が、日本が米の対中戦争に全面的に加担・参戦するものであることは明らかである。
(3) 「一方的な現状変更」は軍事外交政策だけではない。
まずトランプ政権が中国を第1の戦略的主敵とする「価値観外交」を掲げ、対中関税戦争、5G排除とIT制裁などで経済制裁を仕掛けた。そして突如として「新疆ウイグル・ジェノサイド問題」のデマを煽り立てた。ここから香港、新疆ウイグル、チベット、内モンゴルなどで「人権抑圧」「民族抑圧」等々のデマ宣伝を吹聴して公然たる国家分裂策動に乗り出したのだ。
バイデンもこれを全面的に引き継いだ。10月7日には、半導体技術・チップの対中輸出規制を強化し、技術デカップリングに大きく踏み出した。
岸田政権は米国の対ロ制裁、対中制裁に参加し、香港問題、新疆ウイグル問題などでの「人権」非難、中国経済のデカップリングとインド太平洋経済枠組み(IPEF)結成で、政治経済の面でも対中対立を強めている。
(4) 中国軍の台湾周辺での軍事演習やミサイル発射、南シナ海や中国周辺の軍事的展開は、米と西側帝国主義の中国封じ込め戦略、「一つの中国」原則を破る日米一体となった「台湾有事」策動と軍備増強に対する対抗措置だ。それはあくまで中国周辺地域と海域防衛のためである。
中国の対外政策に対して、西側メディアは「覇権主義」などと騒ぎ立てるが、実態は全く逆だ。それは米と西側諸国が自らの軍事同盟と帝国主義的覇権体制、途上国収奪体制に組み込み、従属させることの対極にある。中国は、上海協力機構(SCO)首脳会議、BRICS拡大会議、「一帯一路」などを通じて、平和共存と平等互恵を原則とする「真の多極間主義外交」を展開し、途上諸国・新興諸国との経済開発協力、インフラ建設支援、気候変動対策、医療支援など相互利益=共存共栄(ウィンウィン)の関係を築き上げようと攻勢に打って出ている。それは「台湾有事」をはじめ侵略性と好戦性を異常に高める米帝の野望を阻止し、帝国主義の世界覇権を掘り崩していく「平和共存」戦略に他ならない。
[4] 日米は「一つの中国」原則を守り、台湾分裂策動をやめるべき
(1) 「一つの中国」原則とは、世界に中国は一つしかないこと、台湾は中国の一部であり、中華人民共和国政府が中国全体を代表する唯一の合法的政府であるということだ。
中国は1949年10月、中華民国政府に代わって人民共和国政府が、台湾を含む中国全土の主権を享受し行使することになった。1971年10月には、中華人民共和国が国連に加盟するとともに、国連の「中国の議席は一つ」であることを確認して、国連代表権問題に終止符を打った(国連第2758号決議)。それ以来、今日に至るまで「一つの中国」原則は、国際関係の基本原則、普遍的なコンセンサスである。日中国交正常化にとっても「一つの中国」は決定的に重要な政治的基礎であった。
(2) そもそも今日の「台湾問題」の根源を作り出した張本人は、天皇制の軍国主義日本である。1895年、日清戦争によって台湾を清国から奪取したことが、半世紀に及ぶ「不幸な時期」(周恩来)を作り出した起点であった。これによって日本はアジアで初めて植民地を有する列強の一員となり、帝国主義的発展の基礎を築いた。植民地台湾は、日本帝国主義が朝鮮半島から中国大陸、そしてアジア全域へと侵略と植民地支配を拡大する出発点、最重要の出撃拠点であった。日米戦争においては「不沈空母」として位置づけられた。日本軍は台湾の貴重な歴史的文化財を破壊し窃盗行為を働いたばかりか、建物を破壊し、無差別殺りくを繰り返し、数万人もの人命を奪ったのである。それは1937年南京大虐殺の前兆であった。
問題はそれだけではない。天皇制日本は、植民地台湾において徹底した皇民化教育を行った。その申し子こそが台湾独立を唱えた李登輝であった。今日の台湾独立勢力は、まさに日本の台湾植民地支配、親日・皇民化教育が作り出したといっても過言ではない。
そして戦後は、日本に代わって米帝国主義が台湾に介入した。それは国共内戦における国民党・蒋介石への直接的軍事支援、朝鮮戦争への介入と米第7艦隊の台湾海峡派遣による台湾解放阻止、第1次・第2次台湾危機など、帝国主義的介入は1972年のニクソン電撃訪中、79年の米中国交樹立=台湾との断交まで繰り返された。
それから半世紀、米国は再び台湾をターゲットにした「台湾有事」策動に乗り出し、日本もまたこれと一体化して対中戦争準備を本格化し始めたのである。「台湾問題」を作り出した日米帝国主義の歴史的犯罪を徹底的に暴き出していく必要がある。
(3) 日本のメディアは、中国があたかも台湾の「武力統一」を追求しているかのような宣伝を繰り返している。だが中国の基本方針は、「一国二制度」であり、あくまでも長期的戦略としての「平和統一」である。中国は少なくとも1978年以降、「武力統一」という言葉は使っていない。
台湾問題は中国の内政問題である。中国政府は台湾との間の「92コンセンサス」に基づき、両岸の平和的発展を進めている。日本ではほとんど報じられないが、大陸と台湾の貿易額は習近平体制下で急増し、3283億米ドル(2021年)と過去最高となった。台湾にとってはどの国の貿易額よりも大きく、中台間の経済関係、文化交流等はますます緊密になっている。
「92コンセンサス」を否定する民進党と蔡英文は、米国と結んで「独立志向」を強めるが、それでも大陸との緊密な関係、「平和統一」の流れを根底から覆すことはできない。「平和統一」に難癖をつけ、これを破壊しようと目論んでいるのは米国であり日本である。中国に対する分裂策動、「台湾有事」による軍事対決の押しつけ、日米軍事同盟、AUKUS等による軍事的包囲、等々は公然たる内政干渉、軍事介入である。「台湾問題」の解決はあくまでも両岸の人民に委ねなければならない。
[5] 中国との平和共存政策への転換には何が必要か?
(1) 日本が米の仕掛ける「台湾有事」に全面加担し、日米共同作戦計画で対中戦争準備で突き進むならば、日米と中国との間の軍事的政治的緊張は一気に高まる。このままでは本当に戦争になるだろう。これを何としても食い止めなければならない。
対中戦争を阻止するためには、何よりもまず日本の軍事外交政策を変えなければならない。中国敵視・対中包囲の軍事外交政策を、中国との平和共存、真の友好・協力へと進む政策へと根本的に転換させる必要がある。しかしそのためには何が必要か?
まず第1に、米日が一体となった対中戦争準備の危険性と切迫性を暴き出し、広く知らせていくこと。実際に「台湾有事」になれば南西諸島の島々が対中攻撃拠点となる。米軍は後方に退いて自衛隊に戦わせ、結局住民が被害を受けること、「戦争法」による「事態認定」で日本全土が自動的に戦争に巻き込まれること、等々、米バイデン政権の危険で陰湿な目論見、「台湾有事は日本有事」などと敵基地攻撃能力を獲得し、対中軍備増強を進める岸田政権が戦争の危険性を格段に高めていることを訴えていこう。
第2に、日中共同声明の原点に立ち返り、「一つの中国」原則と侵略戦争に対する反省、さらに日中平和友好条約の「武力や武力による威嚇に訴えない平和的解決」を武器に、岸田政権に中国との平和共存と友好協力を迫っていくこと。
第3は、反中・嫌中イデオロギーとの闘いである。新疆ウイグルの「人権抑圧」、「尖閣諸島は固有の領土」、中国の「債務の罠」など、繰り返される中国敵視プロパガンダに対して具体的事実で暴露し、分かりやすく説明する説得活動を強めよう。
(2) しかしそれだけではまだ不十分である。何故なら、あらゆるメディアが連日連夜、執拗に「中国脅威論」を洪水のように垂れ流し、中国に対する嫌悪・侮蔑・敵視・恐怖・不信・嫉みなどの感情、イデオロギーを人民大衆に刷り込んでいるからだ。世界19ヵ国の世論調査によれば、「中国嫌い」の割合は87%と世界で最も高い(米ピュー・リサーチ・センター今年1~6月調査)。
日本の人民は何故、中国に対する誤った認識を持つようになったのか? 差別・偏見に取り憑かれているのは何故か? どうすれば、これを克服できるか?
重要な要因として、かつての天皇制日本による侵略戦争と植民地支配に対する反省の欠如がある。このことが、今日の中国と中国人を見下す差別的・排外主義的意識を再生産する原因の1つとなっている。われわれは、中国が歴史的に被ってきた侵略と植民地支配、帝国主義的介入による苦難、それが社会主義的発展に大きな困難を強いたこと、今日に至るまで中国人民に甚大な影響を及ぼしていることをあまりに知らなさすぎる。過去のことで済ますことは許されない。国交正常化50年にあたり、中国メディアは繰り返し日本の侵略戦争の反省が不徹底だと指摘し、改憲・軍拡策動に対して警鐘を鳴らした。日中共同声明で中国は賠償請求を放棄したが、それは決して日本の戦争犯罪を不問に付したのではない。共同声明発表後、周恩来が「未来のために過去を忘れるな」と語ったことを、今こそ思い起こさなければならない。
帝国主義日本で活動するわれわれは、抑圧民族としての自己批判を片時も忘れてはならない。もう一度、アジアの近現代史、日本帝国主義と米・西側帝国主義の侵略的本質、植民地主義的本質を学び直し、深く知る努力を続けることが大切である。そうすることで現在の中国の真の姿を捉えることができるだろう。
(3) 中国と帝国主義・資本主義諸国の間には、平和共存の経済的・物的基礎が形成されている。かつての米ソ冷戦時代、ソ連社会主義と西側資本主義との経済・貿易関係がほとんど分離されていた時代とは根本的に異なる。とくに日中経済は緊密に結びついていて簡単には切断できない。日本にとって中国は最大の貿易相手国であり、中国にとっても日本は米国に次ぐ第2の位置を占める。この間、日本の貿易赤字は今年8月に過去最高、13ヶ月連続の赤字で長期的・構造的衰退が顕著になったが、その中で中国への依存度が急速に高まっている。とくに半導体と関連材料、電子部品、設備等は日本の輸出の原動力となってきたが、中国の製造業と市場への依存度を高めている。さらに自動車産業では直接投資と生産における部品供給において対中依存が顕著に進んでいる。このような状況で、日本が米国に付き従って対中戦争の先兵の道を進み、経済面での中国排除に動けば、中国政府の非難を浴びるだけでなく、自国経済を一気に衰退させることになるだろう。
日本の財界は、経団連等の主催で日中国交正常化50周年記念レセプションを開催した。だが結局、岸田首相は出席しなかった。政治の側は明らかに対決に舵を切っている。財界人の中で戦争体験者は皆無に近くなっている。財界の中で対中対決に進む政府を公然と批判する動きはまだない。しかし、日本の対中対決と日中経済依存の矛盾は、いずれ必ず日本の政治経済全体を揺るがす大問題となる時が来る。
日中経済関係の緊密化と矛盾は、それだけで自動的に対中戦争準備を押しとどめることはできない。とくに岸田政権が対中対決姿勢をエスカレートさせている下では、大衆的な世論と運動の力が不可欠である。日本の人民運動が岸田政権の中国敵視政策と闘い続け、政府・支配層に対中平和共存と相互協力への転換を迫り、これが世論へと高まっていくならば、政府の反中政策と日中経済関係との矛盾を拡大し、平和共存と真の友好協力への道を切り開くことができるに違いない。
(4) 他方で、反中・嫌中意識の蔓延とはまた別の現実があることにも注目したい。いま若い世代を中心に、中国のITと最先端技術、言語、文化、歴史、ドラマ、食、スポーツ、ファッション、自然など、多くの分野で関心と親近感が高まりつつある。日中の学生交流も日中友好活動の重要な一環として相互理解を深める重要な役割を果たしている。世論調査では、中国に「親しみを感じる」割合は、全年代平均20・6%(60代は13・4%、70代以上13・2%)に対して18~29歳では41・6%と2倍を超える(内閣府「外交に関する世論調査」2022年1月)。
日本と中国は動かすことが出来ない隣国である。日中間の2000年を超える交流の歴史、文字、宗教、習慣、文化など生活全般における緊密なつながりを踏まえるならば、日中関係は平和共存と友好協力以外の選択肢はあり得ない。このことが広範な人々のあいだで理解され浸透していく土壌は着実に成熟しつつある。
(5) 絶対に対中戦争を引き起こしてはならない。われわれは改めて、反戦平和運動の強化を呼びかける。職場・地域・学園、労働組合、市民運動など各地の広範な現場から、「台湾有事」策動=対中参戦準備に反対する広範な世論と闘いを作り上げよう。岸田政権に対し、対中戦争準備、中国敵視をやめ、平和共存政策に転換するよう要求しよう。統一教会問題の徹底追及、軍事費倍増反対、9条改憲阻止、雇用・労働・生活要求、消費税減税・廃止、原発再稼働反対と原発推進計画撤回、等々あらゆる運動の課題と結合し、岸田政権を追いつめよう。
2022年10月9日 『コミュニスト・デモクラット』編集局